突然の別れに直面したとき、「何を、どの順番で、いつまでにすればいいのか」を事前に知っておくことは、ご家族にとって大きな安心になります。
この記事では、亡くなった日から14日以内に必要な手続きを「8つのステップ」に時系列で整理しました。
実際にその時が訪れる前に、事前知識として心に備えておくことで、慌てずに行動できるようになります。もしものときの“道しるべ”として、ぜひご活用ください。
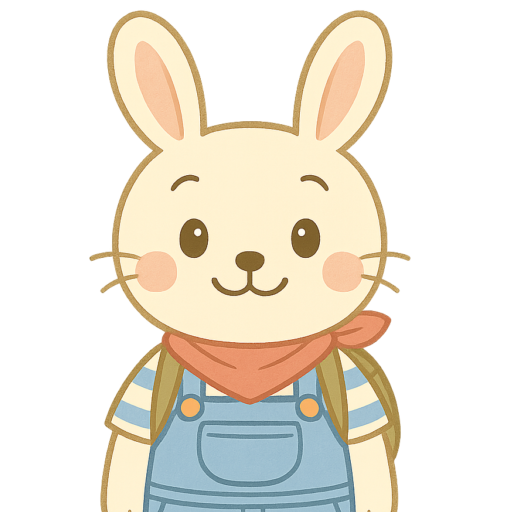
こんなにやることが多いんだね…何から始めればいいの?

まずは死亡診断書をもらうところからだよ〜。これが全部の手続きのスタートなんだ〜。

順番に進められるよう、時系列でまとめたから一緒に確認してみよう!
当日~24時間以内に行うこと
1. 死亡診断書・死体検案書の取得とコピー
- 自然死の場合:医師が発行する死亡診断書(費用3,000~1万円)(出典※1)
- 事故・不明死の場合:警察医による死体検案書(検案料含め3~10万円)(出典※2)
- 後続の相続・保険手続きにも使うため 3~5部コピー を取りましょう。
2. 近親者への訃報連絡
- まずは 配偶者・子・親・兄弟姉妹 など親しい家族へ電話
- 葬儀の日程・形式が決まり次第、友人・職場へ順次連絡
3. 葬儀社の選定と遺体搬送
- 希望の葬儀形式(家族葬・一日葬・直葬 等)を扱うか確認
- 見積りの総額と追加費用の説明が明確かをチェック
- 病院安置は数時間が目安。搬送は葬儀社または病院提携業者へ依頼
2日目~7日以内に行うこと
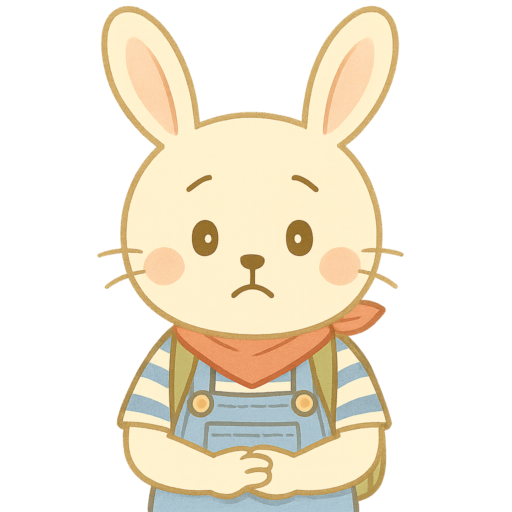
死亡届って自分で出しに行く必要があるの?

葬儀社さんが代行してくれることも多いけど、自分で行く場合は7日以内だから忘れずにね〜

火葬許可証も同時にもらえるから、書類はなくさないようファイルで管理しよう!
4. 死亡届の提出と火葬許可証の取得
- 提出期限:死亡を知った日から7日以内(国外死亡は3か月以内)(出典※3)
- 提出先:故人の本籍地・死亡地・届出人住所地の市区町村役所
- 同時に火葬許可申請を行い 火葬許可証 を受領(出典※4)
- 葬儀社による代行手続きも可能
5. 葬儀の日程決定(通夜・葬儀・告別式・火葬)
- 火葬場や式場の空き状況、宗派・家族の意向で調整
- 喪主は当日 火葬許可証 を必ず持参
- 平均葬儀費用は約119万円(鎌倉新書「全国調査」2024年)(出典※5)
葬儀当日~初七日までに行うこと
6. 初七日法要(繰上げ法要)
- 本来は命日から7日目。ただし近年は 葬儀当日に繰上げ が一般的
- 僧侶手配・返礼品準備など葬儀社に一括依頼可
7. 葬儀費用の精算と領収書保管
- 葬儀後1週間前後で請求書が届く
- 領収書は 国民健康保険「葬祭費」・社会保険「埋葬料」 の請求に必須(出典※6)
- 故人名義口座は凍結されるため、喪主や遺族名義の立替払いが無難
8. 各種名義変更・保険請求(14日以内目安)
- 健康保険証返却、年金受給停止、公共料金・携帯・サブスクの名義変更
- 期限のある手続き(世帯主変更、運転免許返納 等)は役所HPを確認
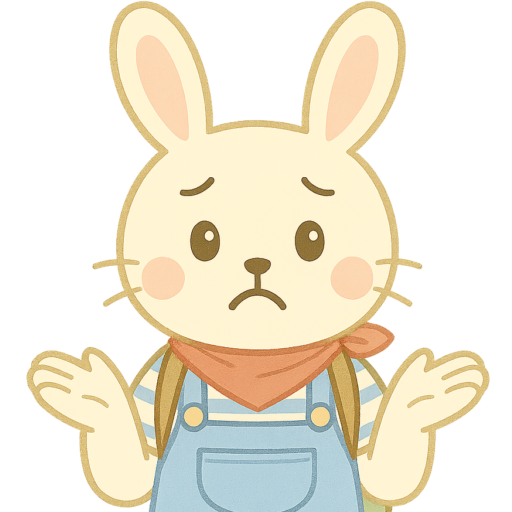
名義変更って全部一度にやるの大変そう…

優先度の高いものから順番に。役所や窓口の“チェックリスト”を使うと便利だよ〜

14日以内にやるものと、ゆっくりでいいものを分けて進めよう!
よくある質問(FAQ)
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 死亡診断書は何通必要? | 公的手続きや保険請求で 2〜3通、相続手続きまで見据えるなら 5通ほど あると安心です。 |
| 葬儀社はすぐ決められない… | 病院提携業者に 搬送のみ依頼し、後日 見積り比較してから本契約でもOKです。 |
| 初七日法要を省略しても良い? | 宗派や家族の考え方次第。省略・繰上げ法要ともにマナー違反ではありません。 |
| 葬祭費の申請期限は? | 原則として 葬儀日の翌日から2年以内。領収書と火葬許可証のコピーが必要です。 |
まとめ
大切な人を見送る手続きは、短期間に多岐にわたります。この記事の8ステップを参考に、まずは 死亡診断書の確保→死亡届・火葬許可→葬儀社手配 の順で優先度を決めましょう。期限のある手続きについては専門家や葬儀社に依頼し、精神적な負担を軽減することも大切です。

この記事、プリントしてお守りにするね!

困ったときは専門家に相談するのも忘れずに〜
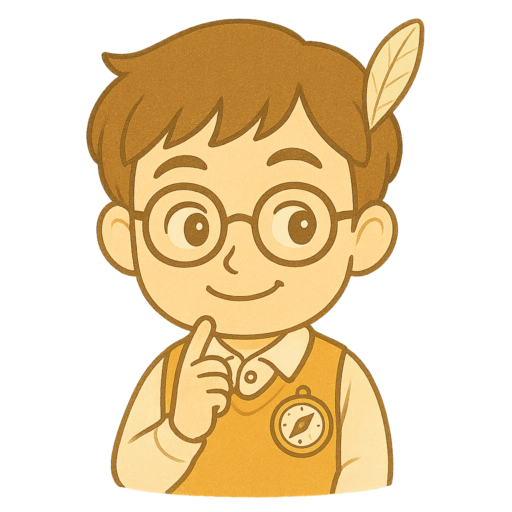
必要な情報は必ずリンク先で最新か確認してね!
参考リンク一覧
・死亡診断書の費用相場(辻・本郷税理士法人)
・死体検案書の費用相場(これからのお葬式)
・死亡届の手続き(法務省)
・火葬許可証の取得方法(辻・本郷税理士法人)
・葬儀費用の全国平均(JILI)
・葬祭費・埋葬料の請求方法(相続手続きガイド)
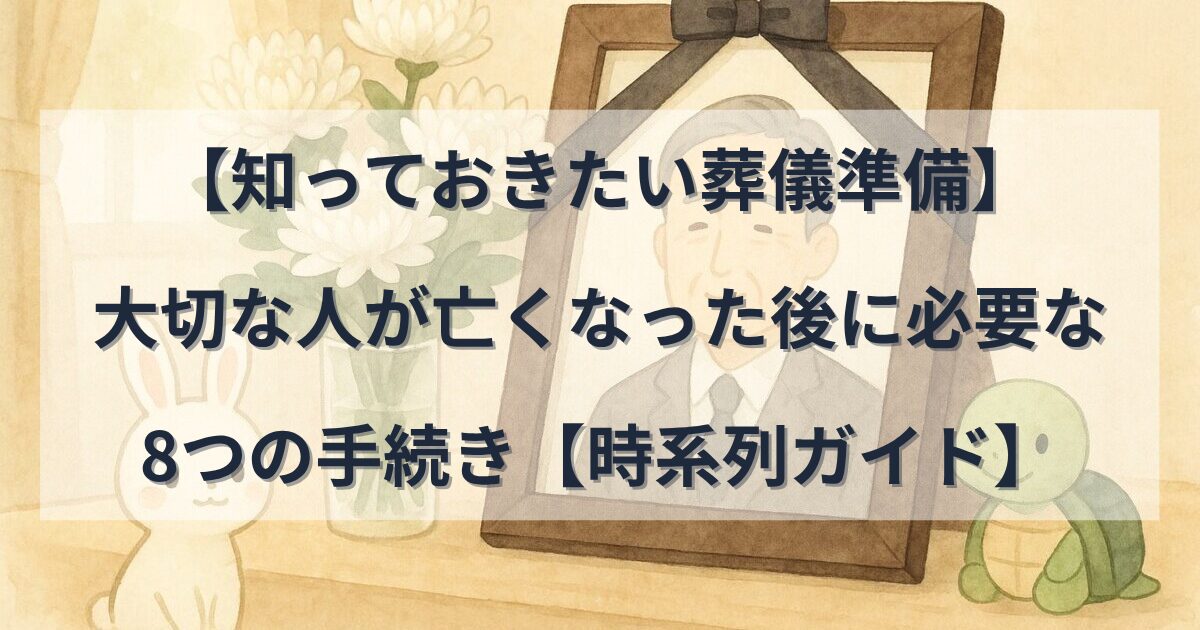
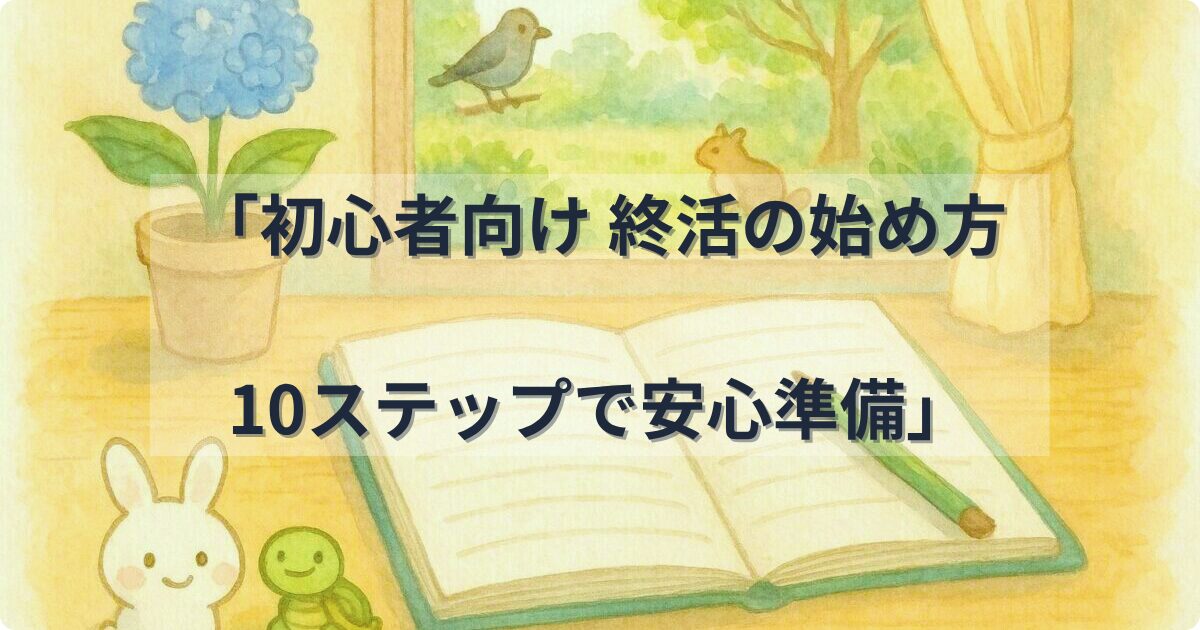
コメント