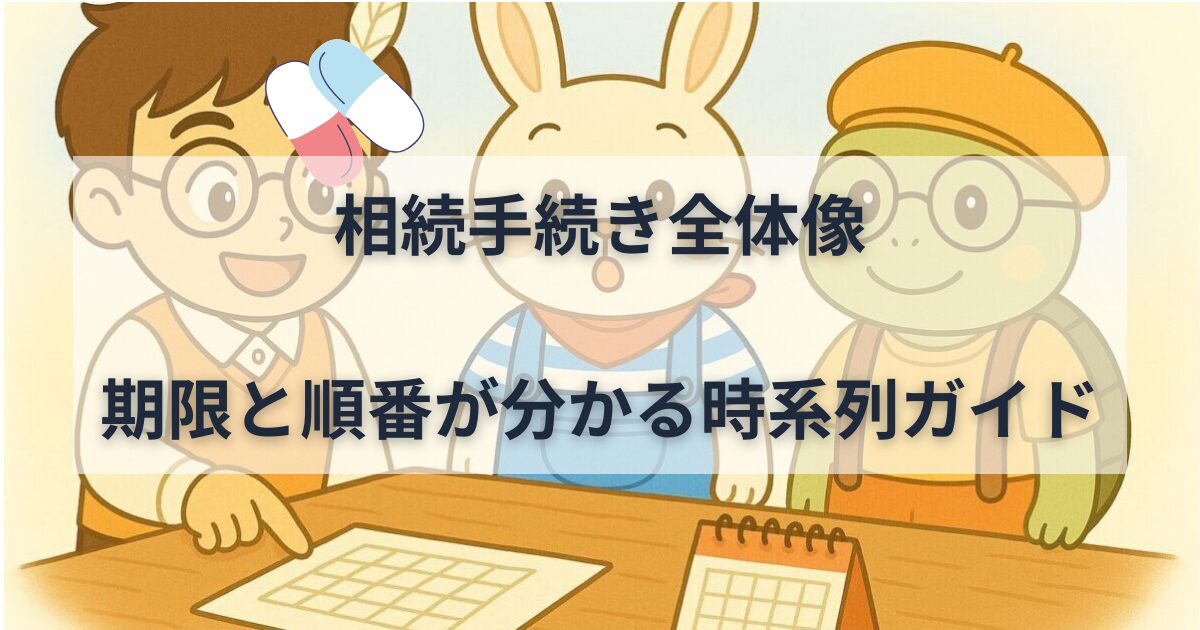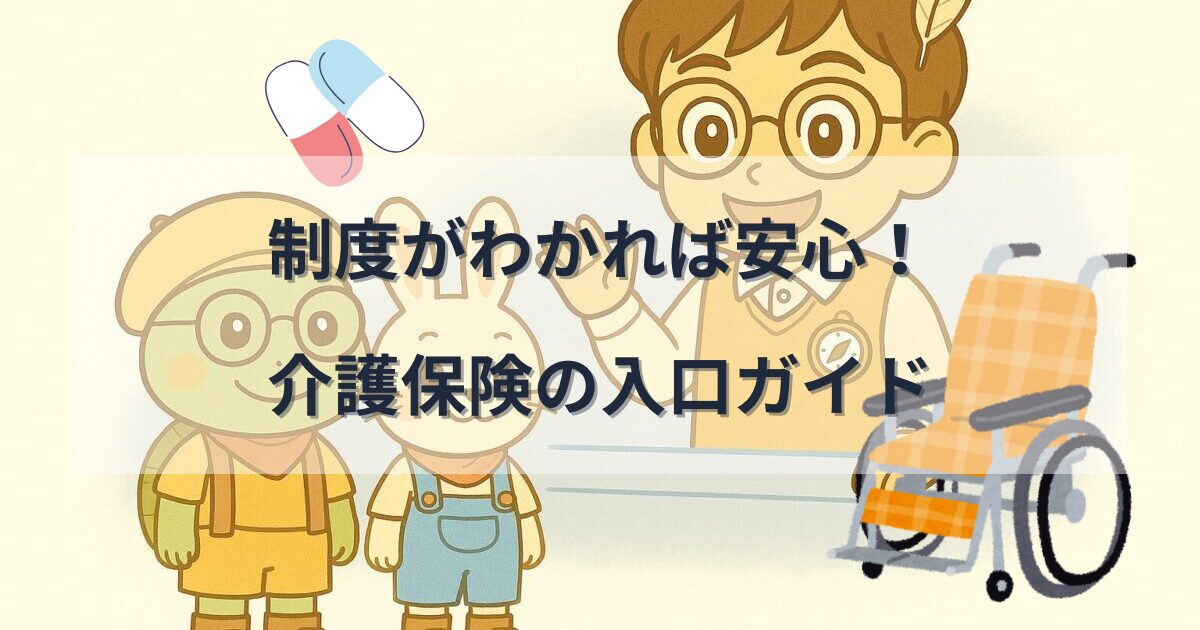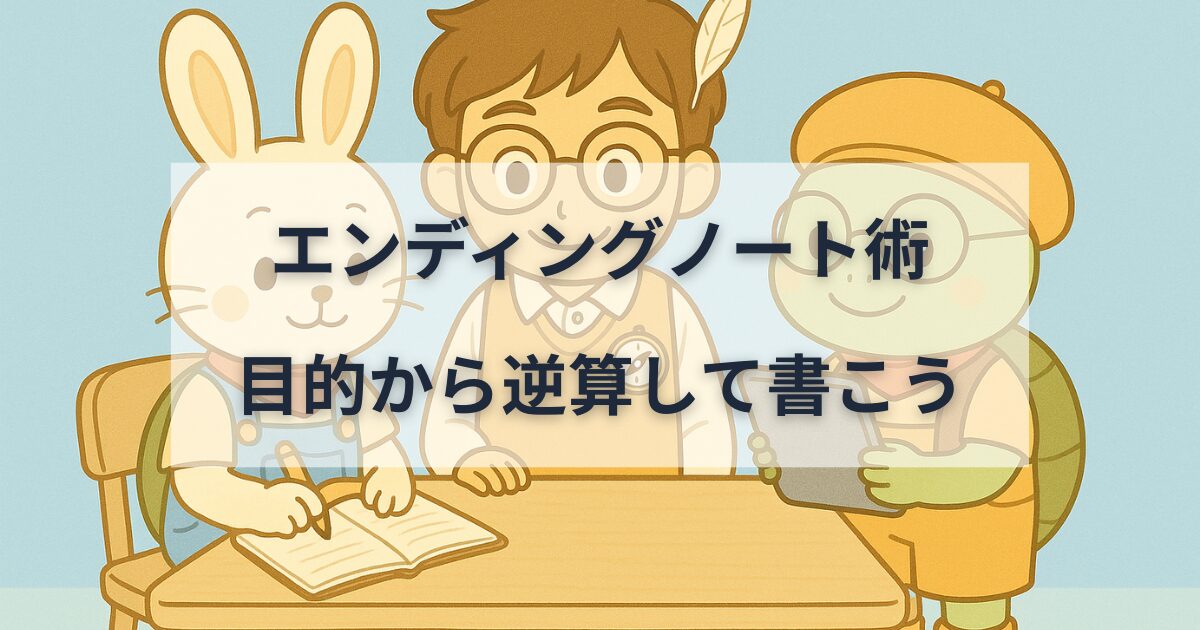この記事は、相続の手続きについて「何を」「どこで」「いつまでに」「どうやって」「何を準備するのか」を、やさしい言葉でまとめたページです。大切な人が亡くなると、手続きは突然やってきます。書類や期限の多さに、心がぎゅっとなることもありますよね。ここでは、むずかしい言い回しを減らして、いっしょに順番どおりに進められるようにお手伝いします。
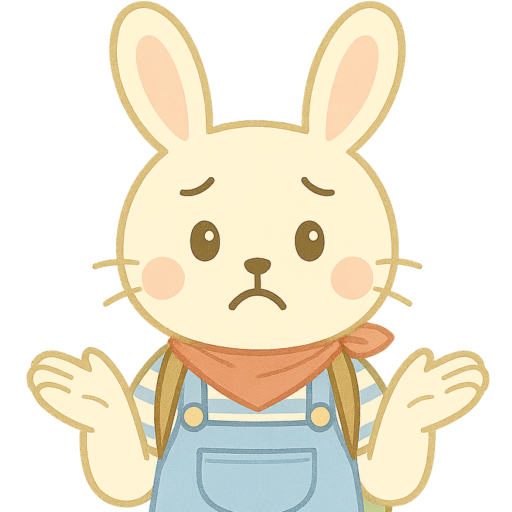
ねぇねぇ、相続のときに銀行の口座が止まっちゃうってよく聞くけど、そうならないように、どう動けばいいのかな?

結構な数のトラブルがあるってよく聞くよね。しかも、戸籍情報を集めたり、年金や保険の解約手続きとかも一緒にくるから、 やることが多い中で色々調べていくって、混乱しちゃそうだよね。
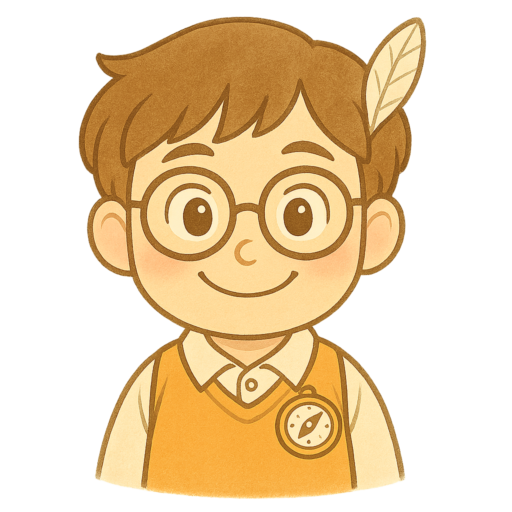
おや、二人とも相続時の話をしているのかい。勉強熱心だね。

相続トラブルは争族トラブルって言うし、念のために知っておこうと思って!
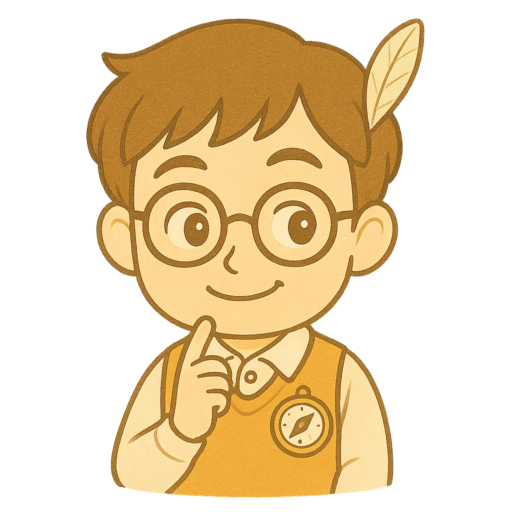
うんうん、仲が良かった家族間が壊れるのは嫌だよね。知っておいて損はないよね。でも、相続手続きは“期限がある手続き”と“窓口がバラバラ”って事もあってとても分かりにくいよね。でも大丈夫。やることを小さく分けて、順番にやれば分かってくるよ。
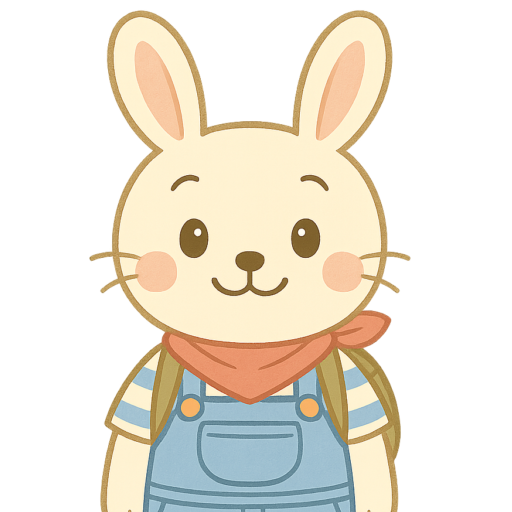
ほんと? 何から手をつければいいか分からなくて困ってたんだ。助かる〜

『次はこれ!』って分かると、ちょっと安心できるね

よし! まずは全体の流れを見て、期限があるものからいっしょにやっていこう
タイムライン総覧(まずは順番の地図)
相続の手続きは、ざっくりこの順番。全部いっぺんにやらなくてOK。期限があるものから先にがコツです。
- 年金・健康保険・介護保険の手続き(止める/もらう)
- 生命保険金の請求(入っていれば)
- 銀行口座・公共料金・ネット/携帯の名義変更・解約
- 戸籍や住民票など、証明に使う書類をそろえる
- (必要に応じて)葬祭費や埋葬料の手続き
- 相続人・財産・借金の確認、相続するか決める(〜3か月)
- 亡くなった年の所得をまとめて申告(〜4か月)
- 遺産分けの話し合い・名義変更
- 相続税の申告と納税(めやす:10か月以内・必要な人)
直後〜14日:生活に直結するものから
まずは「止める・もらう・伝える」。ここができると、家計や連絡が落ち着きます。
年金の受給停止・未支給年金の請求
年金を受給しているかたは、いったん停止をしましょう。(※マイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は、死亡届の提出が原則省略できる扱いです。出典:日本年金機構)
手続きをしないままだと、払いすぎた年金の返金を求められる場合があります。反対に、まだ受け取っていない年金があるなら請求して受け取りましょう。
どこで: 年金事務所
やり方: 「受給停止と未支給年金の請求をしたい」と伝えて案内どおりに提出。
準備: 年金証書、戸籍・住民票、本人確認書類、印鑑、振込口座(なお、亡くなった日以後に振込まれた年金のうち「亡くなった月分まで」は未支給年金として請求できます。出典:日本年金機構/未支給年金の案内)
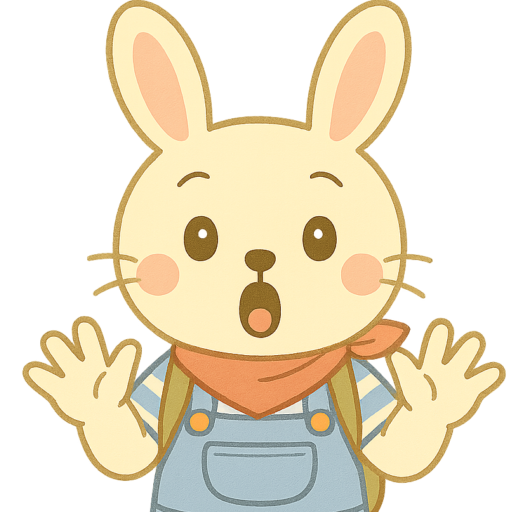
知り合いが、年金を止めるのが遅れて返金のお願いが来ちゃったことあったよね

“もらえる分”も“止める分”も忘れないようにってことだね
健康保険・介護保険(資格喪失と保険証の返却)
健康保険証や介護保険の資格は、早めに止める手続きを。手続きをしないと、保険料がそのまま請求されたり、記録がごちゃつくことがあります。
どこで: 市区町村役場/勤務先の健康保険組合 /
やり方: 「資格を止めたい」と伝え、保険証を返却。
準備: 保険証、(必要に応じて)戸籍、本人確認書類、印鑑(年金の死亡手続は、マイナンバー収録者は原則省略可です。固定の「14日」ではなく、速やかに手続する前提とお考えください。出典:日本年金機構)
生命保険金の請求(入っている場合)
生命保険に加入していたなら、受取人は早めに連絡を。連絡が遅いと支払いまで時間がかかったり、請求の期限に注意が必要です。
どこで: 各保険会社(電話・窓口) /
やり方: 連絡 → 請求書を記入 → 必要書類を提出。
準備: 保険証券、死亡診断書、本人確認書類、印鑑
銀行口座・証券など(凍結解除・払い戻し・分け方の反映)
大切な人が亡くなると、まず最初に直面するのが「銀行口座が使えなくなること」です。
突然のことに「どうしたらいいの?」と戸惑う方も少なくありません。
相続の手続きを進めて、引き出しや分配ができるようにしましょう。放置すると、公共料金や立て替え払いで困ることがあります。
どこで: 各金融機関
やり方: 相続届の書類一式を取り寄せ → 必要書類をそろえて提出。
準備: 戸籍一式、(あれば)遺産分割協議書、印鑑証明、通帳、本人確認書類
※相続預金は、遺産分割が終わるまで「相続人単独での払戻しは不可」となるのが基本運用です。ただし、改正民法の仮払い制度により、各相続人が1金融機関につき上限150万円まで、一定の計算式の範囲内で単独払戻しが可能です。
出典:全国銀行協会(制度概要・必要書類)/出典:法務省(制度の上限150万円の明記)
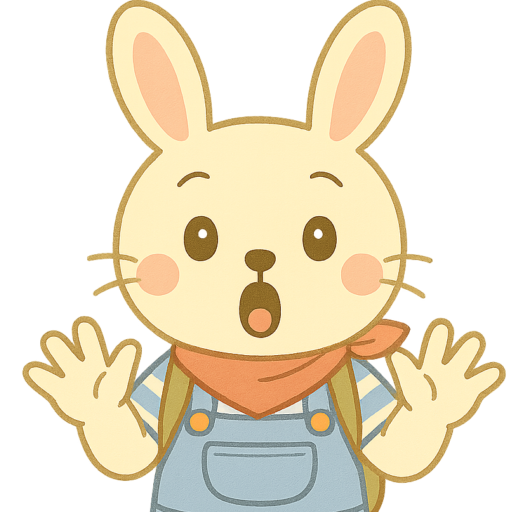
「お葬式代」を口座から引き出せないくなると困る時ありそう
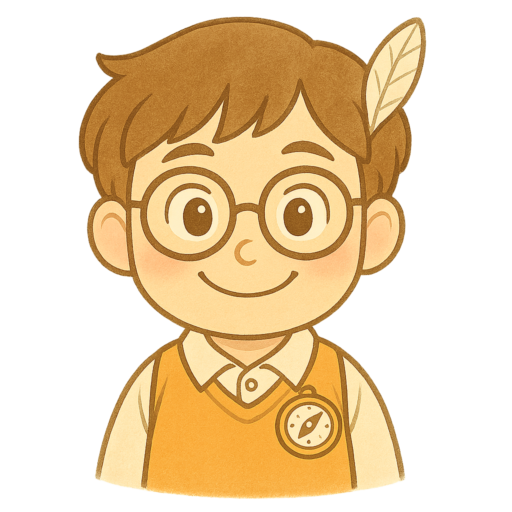
そういう時は「仮払い制度」を上手く使っていこうね
公共料金やネット・携帯(名義変更/解約)
電気・ガス・水道・電話・ネット・NHKなどは、名義変更するか解約しましょう。そのままだと、使っていないのに料金だけが発生することがあります。
どこで: 各社カスタマーセンター
やり方: 死亡の旨を伝え、名義変更か解約を選ぶ。
準備: 契約番号、本人確認書類、口座・クレジットカード情報
死亡診断書・戸籍(死亡の事実の証明)
役所や民間手続きの多くで、死亡の事実を証明する書類が必要です。コピーでもOKか、原本が必要かを確認して用意しましょう。
どこで: 病院・市区町村役場
やり方: コピーを複数用意(役所手続きは返却されることも)
準備: マイナンバーカード、印鑑、手数料
葬祭費・埋葬料(条件が合えば)
健康保険の被保険者が亡くなったとき、家族が葬祭費や埋葬料を受け取れる制度があります(加入制度によって異なります)。
どこで: 健康保険組合/協会けんぽ/市区町村役場
やり方: 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出。
準備: 申請書、死亡診断書のコピー、振込口座、印鑑
Q&A①: 銀行口座から葬儀費用を先に出せる?
A. 原則むずかしいです。各銀行の相続手続きのルールにそって、必要書類をそろえて払い戻しを申し込みます(取り扱いは銀行ごとにちがいます)。
※14日以内」に届出期限があるのは、例として国民健康保険の資格喪失や介護保険の資格喪失などです。出典:北区/出典:マイナポータル。一方、被用者の健康保険・厚生年金は事業主が5日以内に資格喪失届を出します。出典:日本年金機構)
〜3か月:調べて、決める(相続放棄も検討する時期)
この期間は「だれが相続人?」「財産と借金はいくら?」を調べて、相続するかどうかを考える時間です。3か月を過ぎると、原則“相続する”扱いになるので注意。(根拠:民法915条。家庭裁判所に申立てれば熟慮期間の伸長が可能です。出典:裁判所)
戸籍を集めて、相続人をはっきりさせる
だれが相続人かを確かめる最初のステップです。ここがはっきりしないと、銀行や法務局で手続きが止まりがち。
どこで: 市区町村役場(本籍地など)
やり方: 「出生から死亡までの戸籍を取りたい」と伝える。相続人分の戸籍もそろえる。
準備: 申請者の本人確認書類、手数料(現金・定額小為替など)

戸籍を調べていったら、知らない人まで相続の対象だった…なんてこともありそうだね
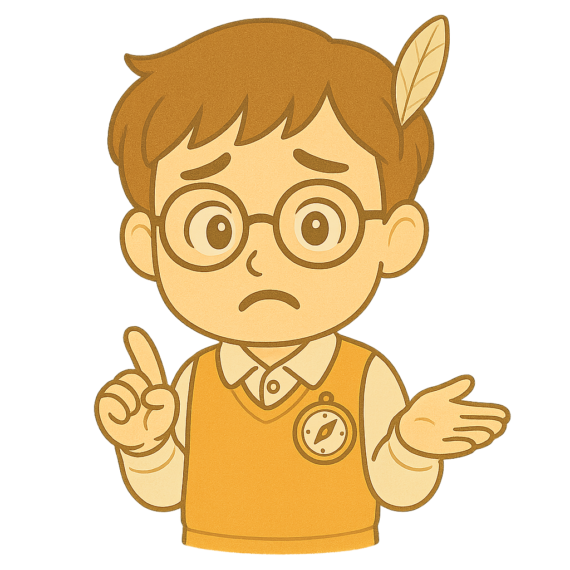
そうなんだよ。家族の仲がよくても、思わぬ相続人が出てくると話し合いがこじれることもあるんだ。
本来ならスムーズに進められるはずだったのに…っていうケースもあるからね。
でも後でトラブルにならないように、ここは丁寧にやっておくことが一番の安心につながるよ
財産と借金の確認(銀行・不動産・借入など)
預貯金・証券・不動産・借金などをざっと一覧にします(メモでOK)。ここを飛ばすと、後から「借金も相続してた…」と気づくことがあるので要注意。
どこで: 金融機関、法務局、債権者など
やり方: 残高証明、登記事項証明、借入残の確認を取り寄せる。
準備: 戸籍の写し、委任状(代理のとき)、本人確認書類、印鑑
遺言書の確認(ある?ない?)
遺言書がありそうなら、まずは有無を確認しましょう。封がある自筆証書遺言は絶対に勝手に開けず、家庭裁判所に持ち込んで「検認」という手続きの流れにそって進めましょう。進行役は裁判所で、相続人みんなで一緒に確認していくのが流れとなります。
どこで: 家庭裁判所(検認が必要な場合)
やり方: 相談窓口で案内にそって手続き。
準備: 封がされた遺言書、本人確認書類、戸籍 など
相続放棄・限定承認(家庭裁判所)
借金が多いときに選べる方法です。期限内に申し出ないと、借金まで相続するおそれがあります。迷ったら早めに相談を。
どこで: 家庭裁判所
やり方: 相続放棄・限定承認の申述書を提出。
準備: 戸籍謄本、申述書、収入印紙、郵便切手、本人確認書類
Q&A②: 相続放棄の期限って、いつから数える?
A. 「亡くなったことを知った日」から数えて、おおむね3か月です。迷ったら、早めに家庭裁判所や専門家に相談を。 起算点は「自己のために相続開始を知った時」です(民法915条)。判断が難しければ伸長申立てを検討しましょう(裁判所)。
〜4か月:準確定申告
亡くなった年の所得を、家族が代表してまとめて申告します(準確定申告)。ふだんの確定申告と同じく、必要な書類をそろえて税務署に提出します。
〜10か月:分け方・名義変更・相続税
遺産分割協議と協議書作成
だれが何を相続するかを話し合い、決めた内容を紙にまとめるところまで進めましょう。協議書は銀行・法務局・税務手続きでも使います。
どこで: 相続人どうし(オンラインでもOK)
やり方: 決めた内容を文書にして、全員が署名・押印。
準備: 戸籍、印鑑証明、財産のメモ、評価の資料
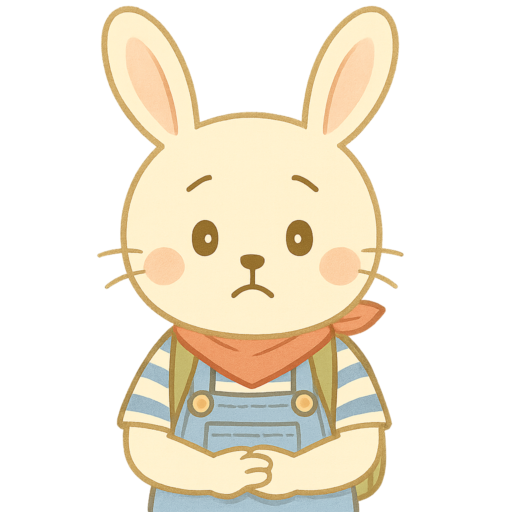
親戚が集まると、思い出話からつい話が脱線するんだよね

でもその“会話の空気”が大事そうじゃない?。重たい空気で進めてもね~。書類に残す前に、みんなの気持ちを整理する時間にもなりそう。
不動産の相続登記(名義変更)
不動産の名義を故人から相続人へ正式に変更します。期限内の手続きが求められるので、書類集めは早めに。(2024年4月1日施行の改正により、相続で取得した事実を知った日から3年以内に相続登記の申請が法律上の義務になりました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。出典:法務省)
どこで: 法務局
やり方: 相続登記の申請書と必要書類を提出(オンライン可)。
準備: 遺産分割協議書、戸籍・住民票、登記事項証明書、印鑑証明 など
自動車・株式などの名義変更
車や株などの名義も忘れずに変更しましょう。放置すると売却や更新、配当の受取で困ることがあります。
どこで: 自動車=運輸支局/株式=証券会社
やり方: 各窓口の案内にそって申請。
準備: 車検証、証券口座の書類、本人確認書類、印鑑
相続税の申告・納税
財産が一定額を超える場合は、申告と納税が必要です。早めに税理士や税務署に相談し、必要書類を確認しておきましょう。
どこで: 税務署
やり方: 申告書の作成・提出、納税。
準備: 財産の評価資料、申告書、本人確認書類、印鑑
書類と窓口チェックリスト(早見表)
- 市区町村役場: 戸籍・住民票、国民健康保険・介護保険の手続き、火葬許可など
- 年金事務所: 年金の受給停止・未支給年金の請求
- 保険会社: 生命保険金の連絡・請求
- 銀行・証券会社: 相続手続きの開始、名義変更
- 法務局: 不動産の相続登記(名義変更)
- 税務署: 相続税の申告・納税
まとめ
- まずは「止める・もらう・伝える」から。年金・保険・銀行・公共料金の順でOK。
- 〜3か月は「相続人・財産・借金」を確認し、必要なら相続放棄や限定承認も検討。
- 〜4か月は「準確定申告」。
- 〜10か月は「遺産分け・名義変更・相続税(必要な人)」。
- つまずいたら、公的窓口や専門家に相談。ひとりで抱えなくてOK。
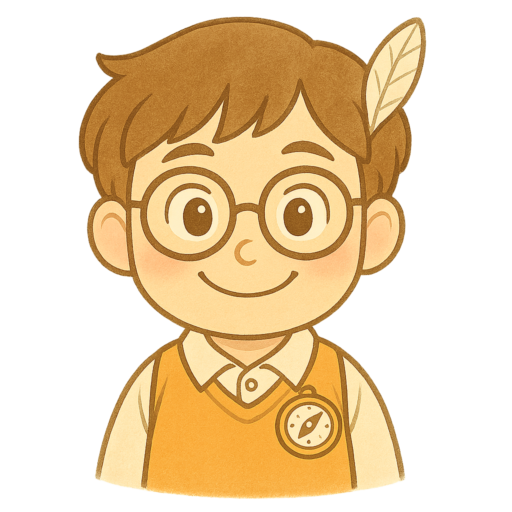
「手続きの名前を見るとむずかしそうに感じるかもしれませんが、大事なのは“順番”を知っておくこと。ひとつずつ進めれば、ちゃんと前に進んでいけます。
困ったら、役所や専門家に相談しても大丈夫。あなたはひとりじゃありません」
CTA(今日の3ステップ)
- 電話を1本: 年金事務所かメインの銀行に連絡して、「相続の手続きを始めたい」と伝える。
- メモを1枚: ノートに「直後〜14日/〜3か月/〜4か月/〜10か月」と見出しを書き、やることを1行ずつ。
- 家族と共有: 写真に撮って家族グループに送る。週1回だけ振り返ればOK。
関連記事
※当サイトは個別の法的助言を行うものではありません。実際の手続きは、必ず公的窓口や専門家(司法書士・税理士・弁護士など)に確認してください。