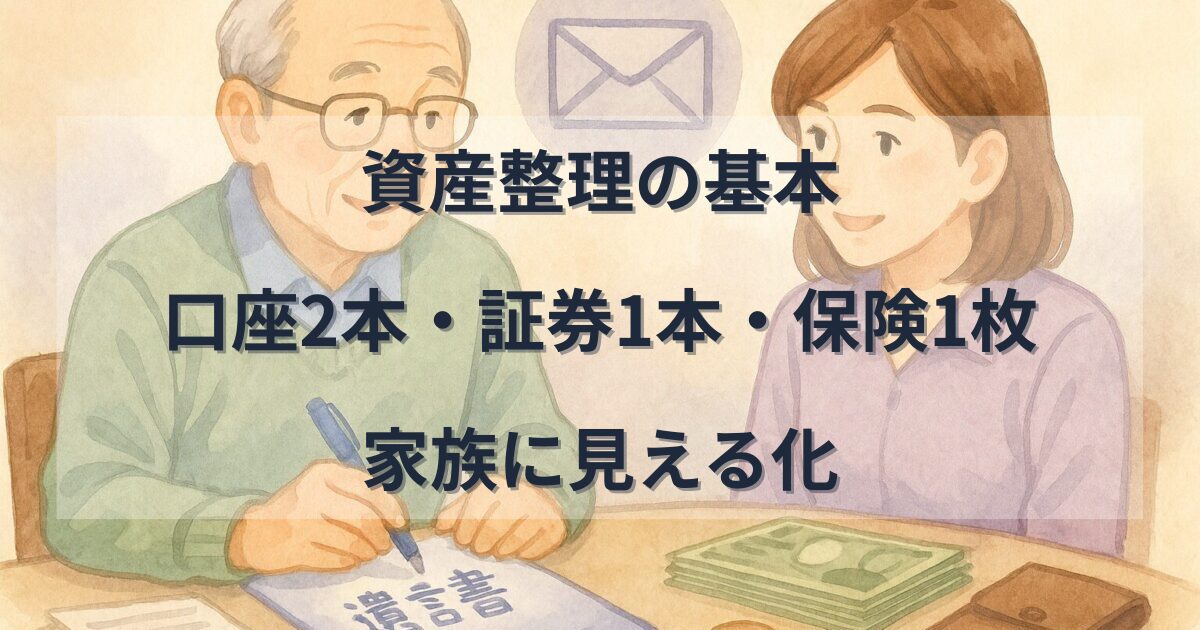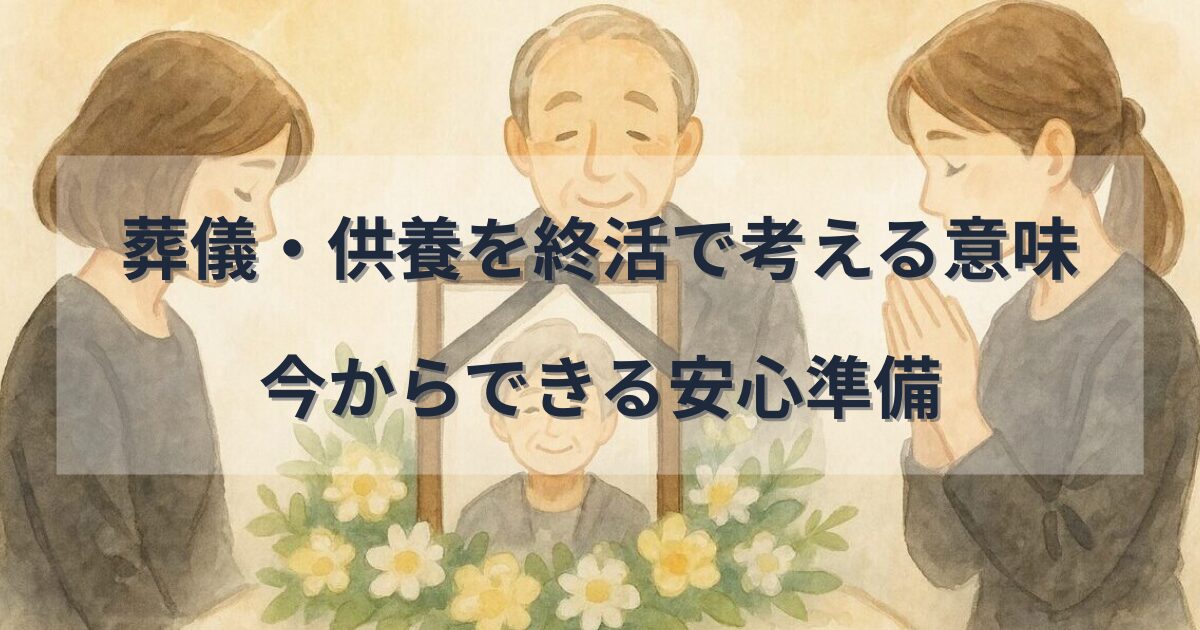この記事は「終活を始めるご本人」と「支援する家族やサポート役」に向けて書いています。
通帳や証券、保険がバラバラだと、いざという時に探すのが大変。
この記事では、資産を 口座2本・証券1本・保険1枚の3本柱にまとめる方法 を紹介します。
読んだあとには、「家族に伝わる安心の整理」がスタートできるようになりますよ。
資産の見える化とは?家族が迷わない整理の第一歩
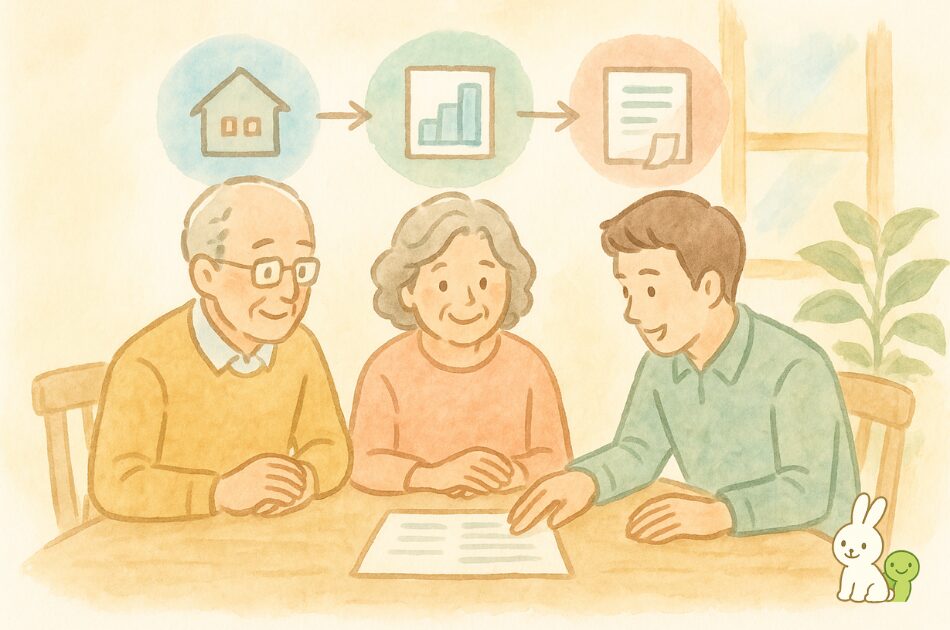
資産の「見える化」とは、お金の流れをひと目で分かるように整理すること。
例えば、毎月の入金(年金や給与)と、支払い(電気・ガス・保険など)を線で結ぶと、「どこから入って、どこへ出ているか」が一目瞭然になります。
メリットは大きく3つ。
- 二重払いを防げる(同じ保険やサブスクの重複が減る)
- 受け取り漏れを防げる(配当金や給付金を見落とさない)
- 家族や支援者が代わりに動きやすい(手順が見える)

朝のコーヒーを飲みながらA4用紙に線を引いたら、気分もすっきり!
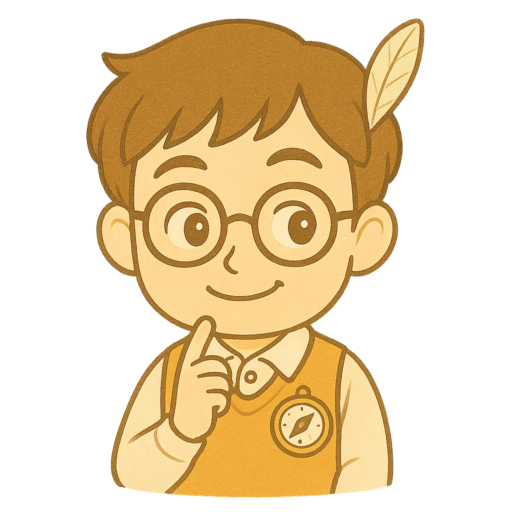
“家族が読めば動けるか?”を合言葉に。略語は使わず正式名称で書こうね。
今日からできる資産チェックリスト(15分で着手OK)

- 通帳とカードを机に並べ、2色ペンで「現役」「停止候補」に分ける
- 毎月の引落し(電気・ガス・携帯・クレカ・保険)をメモ
- A4用紙に「入金 → 決済 → 貯蓄」と矢印で描き、滞りポイントを探す
👉 詳しい表は「口座を2口座に集約する手順」でチェックできます。
銀行口座のまとめ方:2口座体制のすすめ
目標は「入出金・決済用」と「貯蓄・非常用」の2口座に役割を分けること。
全国どこでも基本は同じです。
手順の流れ:
- 住所・氏名を全口座で統一(最初にやると後がラク)
- 引落し先の変更(①電気→②ガス→③携帯→④クレカ→⑤保険)
- 反映まで7〜30日。明細1回分を確認してから次へ
- 不要口座を閉鎖(通帳・カードは裁断または返却)
💡 年金の受取銀行を変えるときは、全国共通の「年金受給権者 受取機関変更届」が必要。支払日の1か月以上前に進めましょう。
証券口座は1本化:新NISAと特定口座のポイント
<p class=”caption”>図解イメージ:新NISAの2つの枠をまとめたイラスト</p>
証券口座が複数あると、損益や税金管理が複雑に。
おすすめは「特定口座(源泉徴収あり)」を1つにまとめることです。
新NISAの基本ルール(金融庁 2024より)
- 1人1口座が原則
- つみたて枠と成長投資枠を別の機関で使うことは不可
- 金融機関の変更は年単位
移管のコツ
- 7日前までに配当受取方式を設定し、投信の積立を停止
- 月末を避け、月の前半に進めると安心
保険の契約一覧を台帳にまとめる

保険は「誰が・どの契約で・いつまで守られているか」が一目でわかる台帳が必須。
例:
「医療|〇〇生命|AB12345|配偶者A|2030/03/31|先進医療|0120-XXXX」
💡 ワンポイント:給付請求の電話番号を先に書いておくと、初動がスムーズ。
家族共有の仕組みづくり

- 紙ファイル:口座マップ、保険台帳、緊急連絡カードをひとまとめ
- 共有フォルダ:PDF版を保存。パスワードはヒント方式で安全に
- 年1回更新:カレンダーに登録し、家族会議で確認
🐢のんきち(②元気)「湯気の立つお茶と一緒に、紙を広げると話が進むね」
👨たけはる(①にこやか)「表紙に“ここだけ見ればOK”と書くだけで安心できるよ」
30日で整える実行プラン
- 1週目:住所・氏名を統一し、引落し先変更を申請
- 2〜3週目:明細確認。証券は積立停止・配当方式を確認、必要なら移管
- 4週目:不要口座を閉鎖、保険台帳を完成。家族と共有
支援者の声(70代母 × 50代長女/28日で完了)
「通帳7冊を2口座に集約、休眠口座も解約。年会費の二重払いが月1,320円減りました。『探す場所が分かるだけで安心した』との声も。」
FAQ:よくある疑問に答えます

Q1. 口座を減らすと「もしもの時」に困らない?
A. 2口座に分ければ十分安心です。入出金用と貯蓄用に役割を決めれば、災害やトラブル時でも生活資金と非常用資金を分けて確保できます。
Q2. 証券口座を1本にまとめると、手数料はどうなる?
A. 各証券会社ごとに最低手数料やポイント制度が異なります。移管時に手数料がかかるケースもあるため、証券会社の公式サイトで事前に確認しましょう。移管後は管理がシンプルになり、結果的にコスト減につながるケースが多いです。
Q3. 保険台帳にはどのくらい詳しく書けばいい?
A. 書きすぎなくても大丈夫です。「保険種類・証券番号・受取人・満期・特約・連絡先」があれば十分。金額や細かな契約内容は必要に応じて別フォルダに。大事なのは“家族が迷わず請求できること”です。
まとめ:今日から進める3つの要点
- 口座2本・証券1本・保険1枚で家族が迷わない
- 付替えは順番と書類名を押さえ、反映確認を忘れずに
- 紙ファイル+共有フォルダ+年1回更新で安心体制に
👉 次の一歩は「A4一枚の口座マップ」を作って、週末に家族と5分共有すること。
きっと気持ちがぐっと軽くなりますよ。
関連記事リスト(テキスト)
- 口座を2口座に集約する手順(届出書の書き方・付替えチェック表)
- 証券一本化・新NISAの年次変更(移管の段取り・取引停止の回避)
- 保険契約台帳テンプレ(印刷してそのまま使えるフォーマット)
免責文
本記事は一般的な情報の提供を目的とし、専門家の助言に代わるものではありません。
個別の判断は専門家へご相談ください。。
執筆者
- 執筆:たけはる/実地検証:2025年8月
出典(一次情報)
- 金融庁「NISAを知る」— 1人1口座/金融機関変更は年単位。(金融庁)
- 金融庁「よくある質問」— 枠の別機関併用不可/異動届の手続き。(金融庁)
- 国税庁「特定口座制度」— 源泉徴収選択と年単位の扱い。(国税庁)
- 金融庁・預金保険機構ほか— 休眠預金は10年無取引でも元の金融機関で引出可。(金融庁, 辞書, 政府のポータルサイト)
- 日本年金機構— 受取機関変更届/住所変更の扱い/手続きは支払日の1か月以上前に。(年金ポータル)