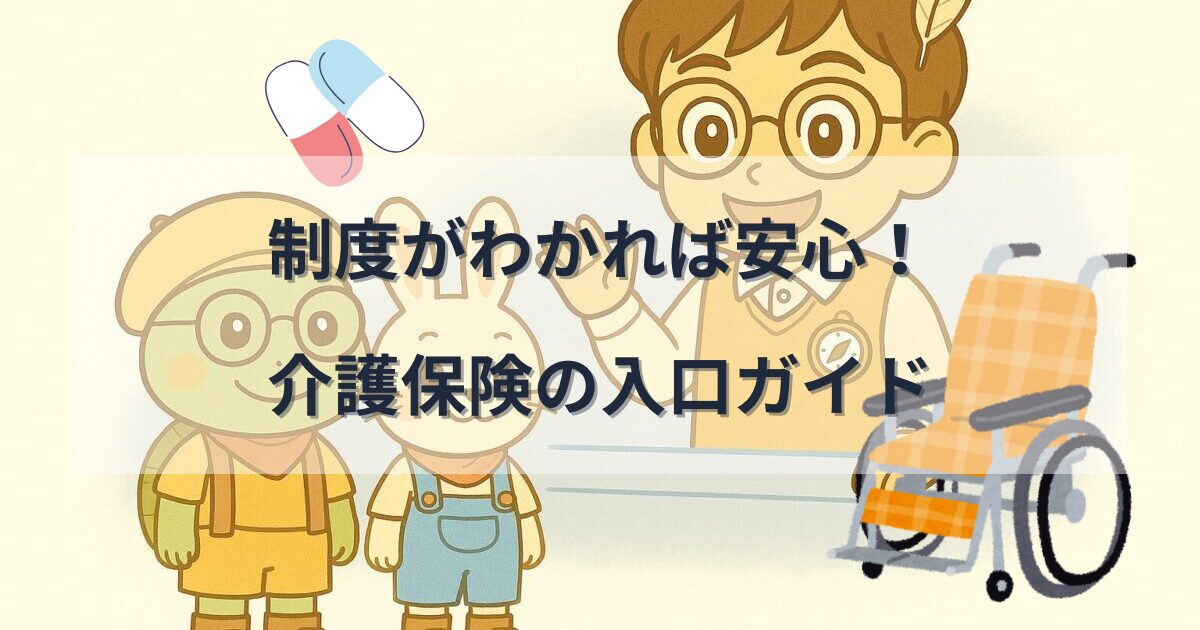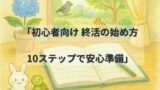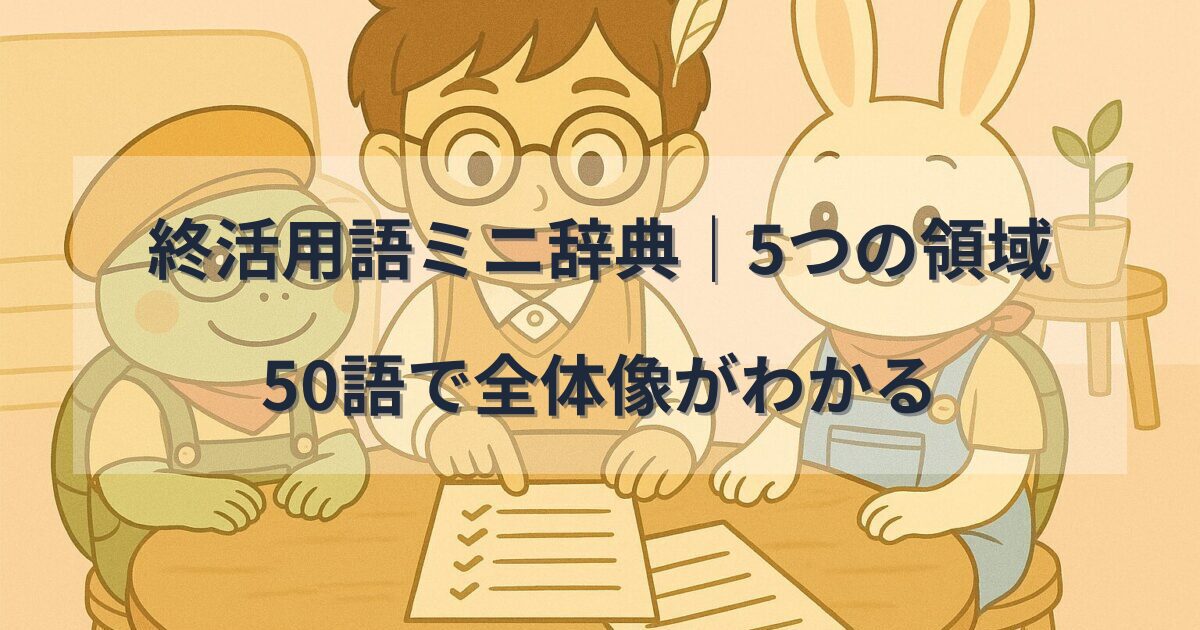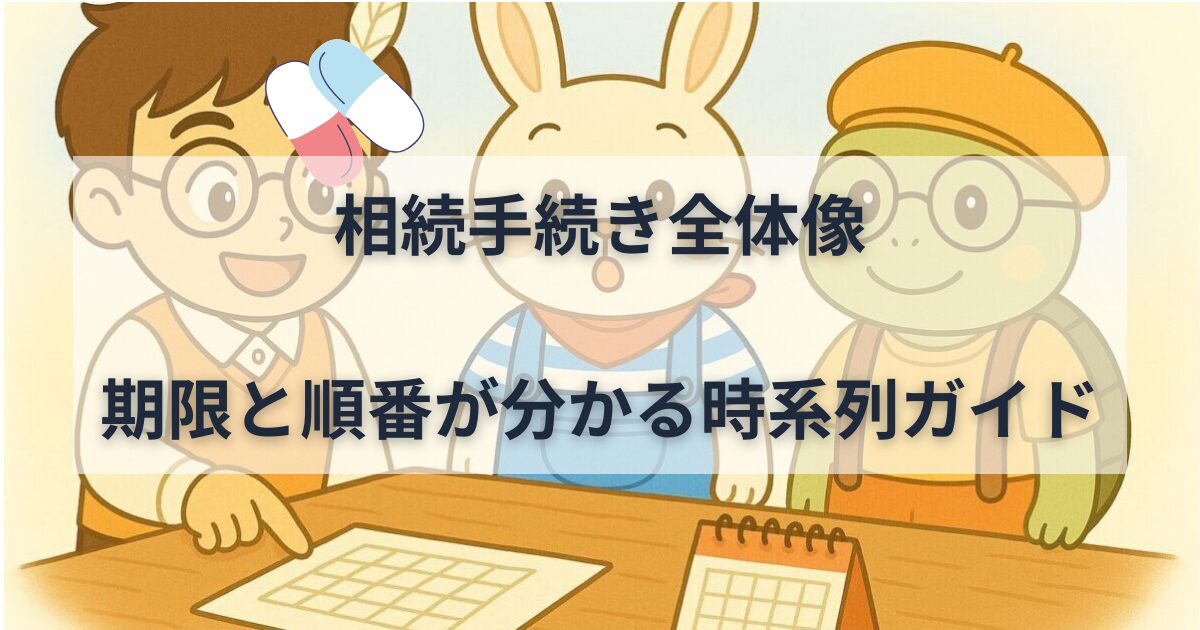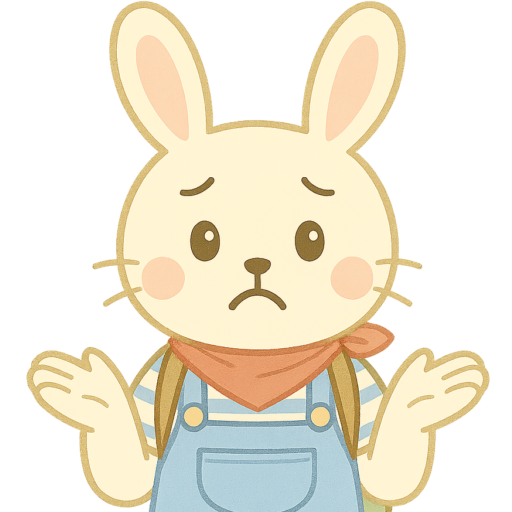
ねぇのんきち、介護保険ってよく聞くけど、結局どういう制度なの?

うん、介護保険制度かぁ。高齢になって介護が必要になったときに使える制度ってことは知ってるけど…細かいことまでは分からないな。なんだか難しそうだよね。
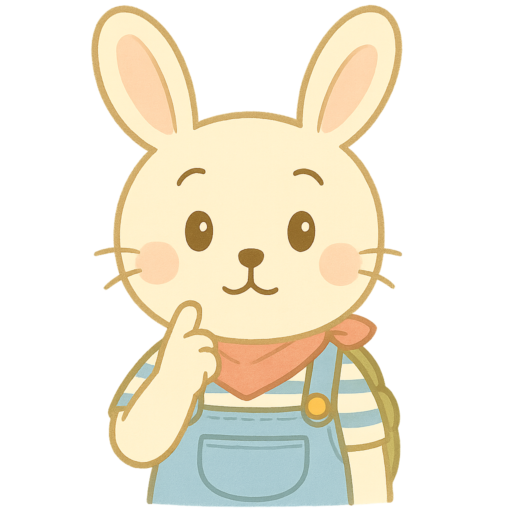
じゃあ、何をどうすればいいんだろう?どういうふうに使えるんだろうね

じゃあ、みんなで介護保険と使えるサービスについて簡単に学んでみようか。
順番やルールがわかれば、実は、介護保険はそんなに難しくないんだ。
介護保険は介護状態にならないと使えないし、まずは専用の窓口で申請が必要なんだよ。

えぇ~、なんか大変そう…。
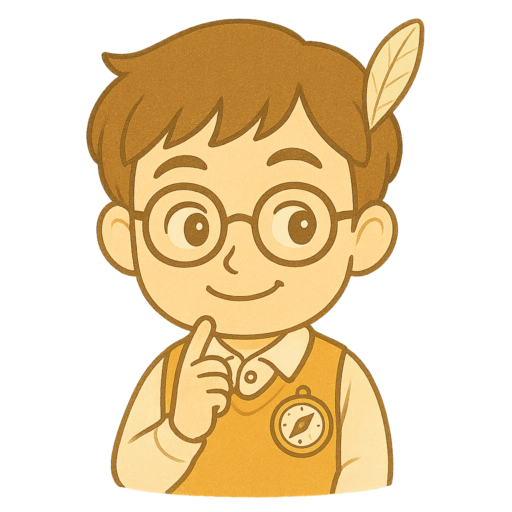
難しそうに聞こえるけど、大筋の流れさえ知っていれば、いざという時に慌てなくて済むよ。今日は全体像をやさしく整理して、不安をぐっと減らしていこう。
介護保険~申請から利用まで~
介護保険は「申請 → 認定 → 利用」という3つのステップで進みます。
まずは、どこで申請するのか、何を準備すればよいのかを押さえておくことで、手続きがぐっとスムーズになります。ここでは最初の一歩となる「申請」から順番に見ていきましょう。
「6ステップで流れが見える!」
| ステップ | 内容 | 扱う情報 | メモ |
|---|---|---|---|
| ① 申請 | 市区町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターで「要介護(要支援)認定」を申請 | 本人・家族の基本情報、被保険者証、本人確認書類、マイナンバー、主治医名、連絡先 | 書式名や提出先は自治体で異なるため、公式サイトで様式と持ち物を事前確認 |
| ② 認定調査 | 職員が自宅などを訪問し、心身の状態や日常生活の様子を聞き取り | 移動・食事・排泄などの自立度、認知機能、既往歴、介助頻度 | 普段の生活リズムや困りごとをメモしておくと伝え漏れ防止 |
| ③ 主治医意見書 | 自治体依頼を受け、主治医が医学的所見を作成 | 診断名、生活機能、治療状況、服薬、今後の見込み | かかりつけ医がない場合は窓口で相談可 |
| ④ 要介護度の判定 | 一次(コンピュータ)と二次(審査会)で区分決定 | 認定調査票、主治医意見書、特記事項 | 結果は通知書で届く。合わない場合は区分変更申請可 |
| ⑤ ケアプラン作成 | 要介護はケアマネ、要支援は地域包括が中心に作成 | 目標、利用サービスの種類・回数、事業所候補、費用見込み | 「したい生活」を最初に共有するとプランが組みやすい |
| ⑥ サービス利用開始 | 事業所と契約し、利用を開始。定期的に見直し | — | 契約書・重要事項説明は保管。変更やお試しの相談は随時OK |
※注意:申請窓口・様式名・必要書類は自治体で異なります。各自治体の案内ページで最新情報をご確認ください。
介護レベル認定(区分と目安)
要介護認定は「どれくらい介護の手間が必要か」を基準に区分されます。下表は全国共通の枠組みに基づく平均的な目安です(自治体で表現が多少異なる場合があります)。
| 区分 | 状態のめやす(平均的な説明) | 一次判定の目安時間※ |
|---|---|---|
| 要支援1 | 家事や身支度など一部に手助けや見守りが必要。暮らしの自立は概ね可能だが、週に数回ほどの予防的な支援があると安心。 | 25分以上〜32分未満 |
| 要支援2 | 生活の一部で手助けが必要。移動や家事の負担が増え、週数回〜の支援で自立が維持しやすい。 | 32分以上〜50分未満 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行などに見守りや部分介助が必要。入浴や排せつなどに時々介助が必要。 | 32分以上〜50分未満 |
| 要介護2 | 起居や移乗に介助が必要。排せつや入浴に継続的な介助が必要。 | 50分以上〜70分未満 |
| 要介護3 | 自力移動が難しく、ほぼ全面的な介助が必要。見守りも常時必要なことが多い。 | 70分以上〜90分未満 |
| 要介護4 | 日常のほぼ全般にわたり手厚い介助が必要。移動や姿勢保持が難しく、排せつ・入浴・食事などで全面的な支援が必要。 | 90分以上〜110分未満 |
| 要介護5 | 常時介護が必要。意思疎通が難しい場合や、複数介助者による対応が必要な場面が多い。 | 110分以上 |
※「一次判定の目安時間」は、認定調査(74項目)と主治医意見書の情報から統計的に推計される「要介護認定等基準時間」です。
家庭で実際にかかる介護時間とは一致しませんが、区分判定の“ものさし”として用いられます。最終区分は審査会(二次判定)で決まります。
根拠(一次情報):要介護認定の判定枠組みと各区分の基準時間(25分未満〜110分以上)は、厚生労働省の公表資料に基づく。詳細は 厚労省「要介護認定はどのように行われるか」/ 「認定調査員テキスト(令和6年4月改訂)」/ 「要介護認定に係る法令等」。
一次判定で用いる「要介護認定等基準時間」は、認定調査(74項目)や主治医意見書の内容から統計的に算出される指標で、家庭での実介護時間そのものではありません。
主なサービス(代表例・少し深掘り)
訪問介護(ホームヘルプ)
ヘルパーが自宅に来て、身体介護(入浴・排泄・更衣など)や生活援助(調理・掃除・買い物)を行います。 「できるところは自分で、難しいところをサポート」する考え方で、在宅生活の負担を軽くします。
通所介護(デイサービス)
日中に施設へ通い、入浴・食事・機能訓練・レクリエーションを受けます(送迎ありが一般的)。 本人は運動や交流の機会が増え、家族は日中の介護負担を軽減できます。
短期入所(ショートステイ)
介護施設に数日〜の宿泊をして、入浴・食事・排泄などの介護と見守りを受けます。 家族の休養や冠婚葬祭・出張時のバックアップ、在宅継続の「支え」として活用されます。
福祉用具の貸与・購入/住宅改修
手すり・スロープ・ベッド・歩行器などで「転ばない工夫」を整え、必要に応じて段差解消や浴室改修を行います。 住環境の改善は、介護量の軽減と自立度アップに直結します(事前にケアマネ等へ相談)。
介護区分別の費用負担について
介護サービスを利用するときの自己負担や払い戻しの仕組みは、ちょっと複雑に感じるかもしれません。でも、ポイントを押さえれば「どのくらいかかるのか」がイメージしやすくなります。
自己負担は所得によって変わる
介護サービスの自己負担割合は、所得の状況によって段階的に決まります。割合は市区町村から通知されますので、まずは自分がどの区分に当たるのかを確認しましょう。
利用計画を立てるときに、毎月のおおよその負担額をケアマネジャーや窓口で聞いておくと安心です。
| 区分 | 10割額の目安 | 1割負担の目安 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
自己負担割合:所得により1〜3割に分かれます。一定所得以上の方は2〜3割になる場合があります。
高額介護サービス費:世帯単位で自己負担額の上限が決まっており、超えた分は払い戻しがあります(世帯合算可・所得区分ごとに上限額が異なる)。
限度額(区分支給限度基準額):介護度ごとに定められた月額の枠内でサービスを組み合わせます(上表は1割負担時の目安)。
- 地域差:地域区分により1単位あたりの円換算は概ね10.00〜11.40円程度で変動します。
- 限度額超過:限度額を超えた分は介護保険の適用外となり全額自己負担です。
- 別枠:特定福祉用具購入(年10万円)・住宅改修(原則生涯20万円)は別枠で管理されます。
出典:介護保険の給付額(月額上限)の目安 / 厚生労働省「介護保険の解説|サービスにかかる利用料」
※具体的な自己負担割合・上限額・食費等の基準は毎年度の制度に従います。最新の公的情報をご確認ください。
高額になった分はあとから戻ってくる
同じ月の自己負担の合計が一定額を超えると、その超えた分は「高額介護(予防)サービス費」として払い戻されます。
家族の分をまとめて計算できる「世帯合算」ができる場合もあるので、対象になるかも確認しておきましょう。
施設利用は別の費用がかかるから注意
入所や通所の場合は、介護サービス費とは別に食費や居住費がかかります。
低所得者向けに負担を軽くする制度もありますので、必要に応じて申請を検討しましょう。
病気によっては40〜64歳の方も対象になる場合がある
65歳未満でも、特定の病気が原因で介護が必要になった場合は介護保険を利用できます。
該当するかどうかは、市区町村の介護保険窓口で確認しましょう。
相談先と準備しておくと安心なこと
介護保険の手続きやサービス選びは、ひとりで抱え込む必要はありません。
まずは、お近くの地域包括支援センターか市区町村の介護保険窓口へ行ってみましょう。
相談は無料で、申請からケアマネジャーの紹介まで、一連の流れを丁寧に案内してくれます。
持っていくとよいもの
- 介護保険被保険者証
- 本人確認書類
- マイナンバー確認書類
- 主治医の名前や連絡先
- 服薬内容のメモ
- 普段の困りごとを書いたメモ
事前にまとめておくとスムーズ
- 生活の様子(できること・難しいこと)を、1週間分くらいメモ
- 家族構成や、手伝える曜日・時間帯の整理
相談を上手に進めるコツ
「どんな生活を送りたいか」「安全面で不安なこと」「家族側の負担の限界」など、思っていることを素直に伝えましょう。代理での申請や、一緒に窓口へ行くこともできます。

とりあえず、困ったら地域の“地域包括支援センター”に行けばいいんだね。
見落としやすい注意点(小さな体験談)
区分変更で風通しが良くなった例
退院直後は本当に不安で、手厚い支援からスタートしました。でも数か月たつと体が動くようになってきて、『もっと自分でやってみたい』と思うように。
ケアマネさんに相談して区分変更を申請し、ケアプランも軽くしてもらったら、無理なく自立へ移行できました。
「世帯合算」を知らず損しかけた例
同居の親子で同じ月にサービスをたくさん使ったら、自己負担がぐんと増えてしまって…。
『やっぱり介護ってお金がかかるなぁ』と落ち込んでいたら、ケアマネさんが“世帯合算”の制度を教えてくれました。明細をまとめて相談した結果、上限を超えた分は払い戻しに。翌月から契約を見直して、家計も安定しました。
介護保険 よくある質問(Q&A)
Q. いつ申請すればいい?
A. 生活に支障を感じたら、早めに申請しましょう。
要介護認定は申請から結果が出るまで時間がかかるため、余裕をもって動くことが大切です。
Q. 自己負担はどれくらい?
A. 所得や利用するサービスの内容によって、自己負担は1〜3割に変わります。
くわしい金額や条件は、お住まいの自治体に確認しましょう。
まとめ
- 「申請→認定→利用」の道順を理解できれば不安は軽くなる。
- 訪問・通所・短期入所・福祉用具/住宅改修など、在宅生活を支える選択肢が豊富。
- 費用は段階制+上限制度あり。世帯合算や軽減制度の確認を。
- 困ったらまず地域包括支援センターへ相談。
CTA:地域包括支援センターの連絡先を1件控え、必要なときすぐ相談できる体制を整えましょう。
注:本記事は一般的な流れの解説です。申請先・書式・必要書類・負担上限額などは自治体・年度により異なるため、最新の公的案内をご確認ください。
関連記事リスト(テキスト)
本記事は一般的情報の提供を目的とし、専門家の助言に代わるものではありません。個別の判断は専門家へご相談ください。