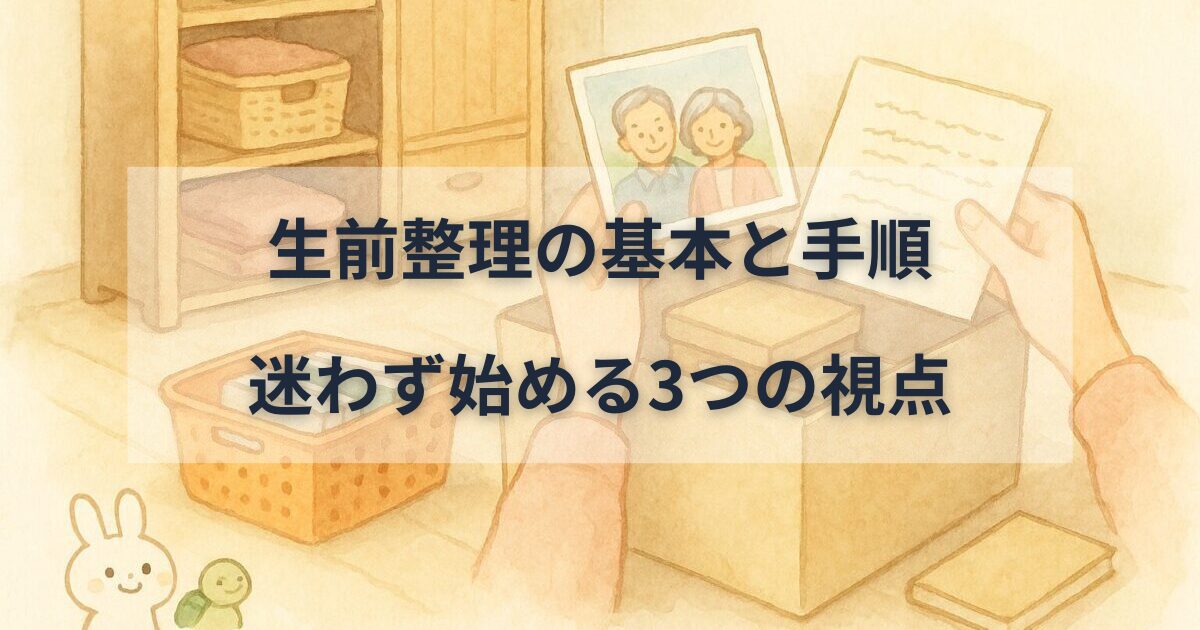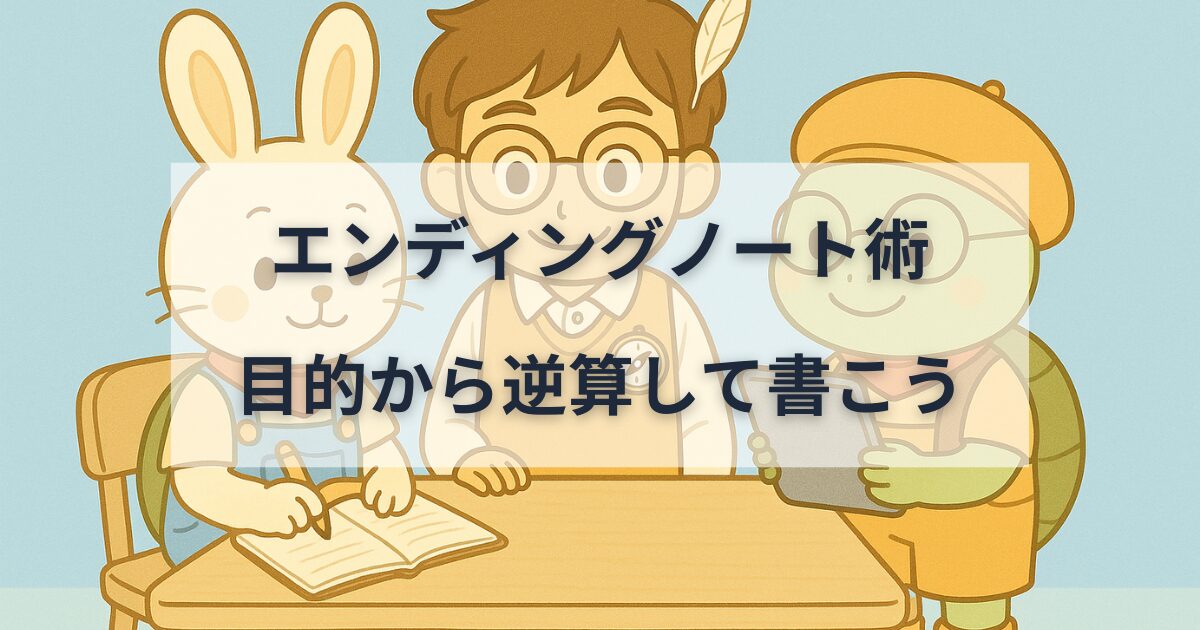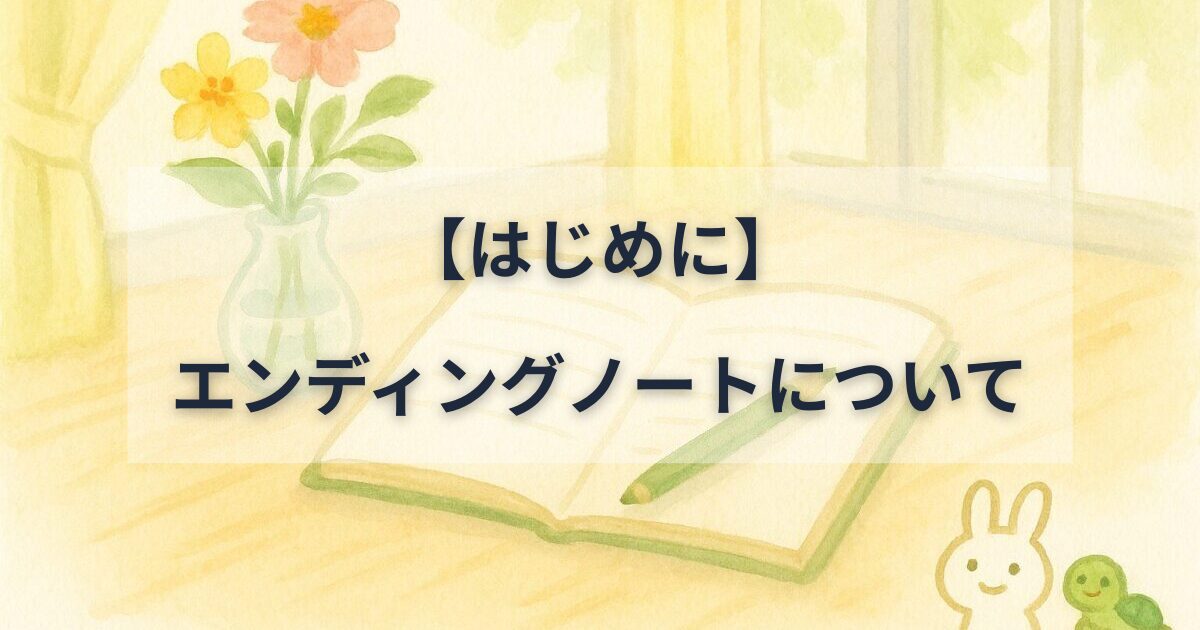迷いが減る整理の第一歩
「生前整理を始めよう」と思っても、モノが多すぎて手が止まる…そんな声をよく聞きます。
実はポイントは「片付け」から入るのではなく、まず何を残し、誰に託すかを決めること。目的が見えると迷いが減り、スムーズに整理が出来ます。
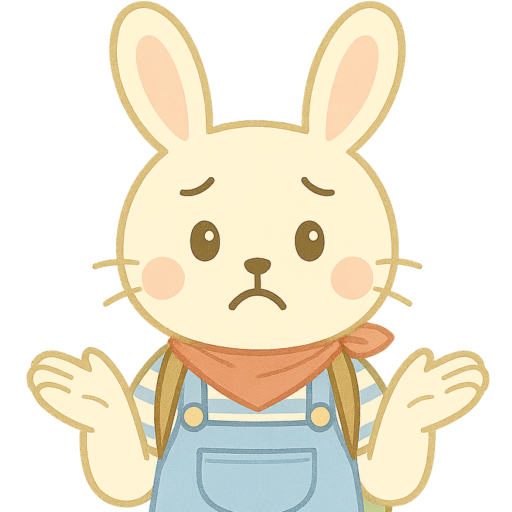
整理したいけど、何から手をつければいいのか全然わからないよ~!

物が多すぎて、見るだけで頭がくらくらするよ。

二人とも頑張ってるね~。そういう時は、“人・時間・物語”の3つのレンズで整理品を見ると、軸がはっきりして仕分けがはかどるよ。
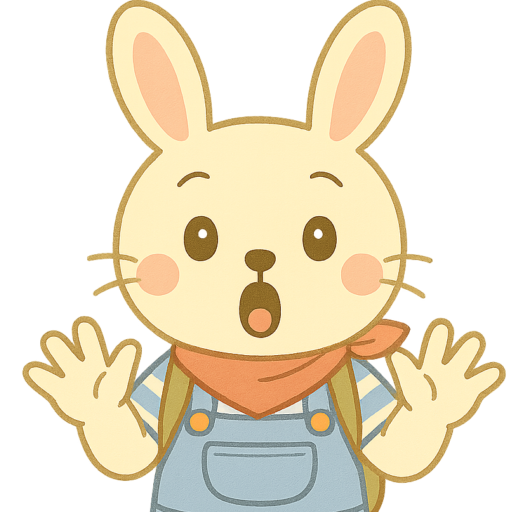
えっ?3つのレンズってどういうこと?
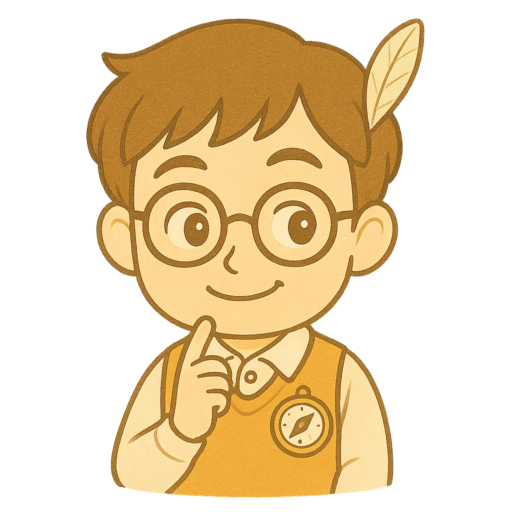
ふふふ。じゃあ一緒に学んでいこう。
なぜ人は物を捨てられないのか?
多くの人が「片づけたい」「すっきり暮らしたい」と思いながら、物をなかなか手放せません。
その理由は、単純に“もったいない”だけではなく、人のつながり・時間の記憶・物語の感情が複雑に絡んでいるからです。
そこで役立つのが、3つのレンズで見直す方法です。
この視点を持つことで「残す理由」と「手放す理由」がはっきりし、心の整理もしやすくなります。
3つのレンズで見直そう
① 人のレンズ
その品は 誰にとって価値があるか を考えましょう。
- 自分にとって必要?
- 家族にとって意味がある?
- 第三者に譲れるもの?
👉 「誰にとって大切か」を見極めれば、ただの“モノ”が“人との関係”の形に変わります。
② 時間のレンズ
これからの暮らしの中で どのくらい使うか を意識しましょう。
- 使用頻度は?
- 季節限定?
- 未来の計画に必要?
👉 「これから先も使う時間があるか?」を基準にすると、今の暮らしに合うモノだけが残ります。
③ 物語のレンズ
物には思い出やエピソードが宿っています。
ただし、それを残す方法は「現物を持ち続けること」だけではありません。
- 写真に撮る
- 一言エピソードをノートに残す
👉 記憶を 言葉や写真に置き換えることで、モノは手放しても物語は残せます。
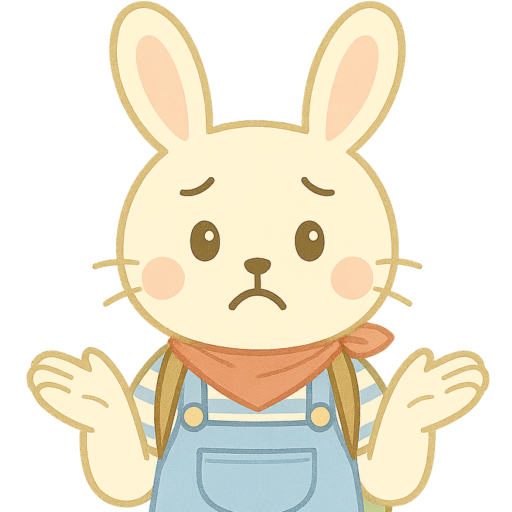
う〜ん、迷う物が多いなぁ…。これも大事に見えるし…。

それこそ、写真で残すのはどう?物語は残して、場所は空けられるよ。
生前整理を3つの箱に仕分けして進めよう
「3つのレンズ」で物との向き合い方を整えたら、次は実際に行動に移しましょう。
暮らしや終活の整理を進めるときは、頭の中を一気に片づけようとすると混乱しがちです。
そこでおすすめなのが、モノ・情報・心を分けて考える 『3つの箱』仕分け法。
レンズで気持ちを整理し、箱に分けて実務を進める。この組み合わせで、ぶれずに取り組めます。
🗃 モノの箱
生前整理で最初に取り組みやすいのが「モノの箱」です。
衣類や食器、書類、家具、写真などを「いる/いらない/保留」に分けるだけでも気持ちが軽くなります。
特に写真は数が膨大になりやすいため、アルバムにまとめたりデータ化したりすることで、大切な思い出を残しながら整理できます。
小さなものから手をつければ「片づけの手応え」を実感でき、次の整理にもつながります。
📑 情報の箱
次に重要なのが「情報の箱」です。財産目録や重要書類、デジタルアカウント、保険や年金などは家族にとっても必要不可欠。
とりあえず “所在リストを1枚作る” だけでも全体の見通しがよくなります。
遺言書の準備もここに含まれます。遺言は民法で定められた法律文書であり、自筆証書遺言は法務局で保管できる制度があります※遺言は民法に定める「法律文書」です。自筆証書遺言は法務局で保管できる制度があります。 出典:e-Gov(民法)/ 出典:法務省(自筆証書遺言書保管制度)
一方で、エンディングノートには法的効力はありません。気持ちや希望の記録には役立ちますが、財産分けは遺言書で行う必要があります。
💌 心の箱(要約版)
終活を進める前に欠かせないのが「心の整理」です。使うのは1冊のノートだけです。
ここは立派な文章を書く場所ではなく、自分だけの心の世界を映す場所。
今の思いを書き出せば、心は少しずつほぐれて終活に対する自分の考えを整理できます。
小さな一行が“自分史の下書き”となり、やがてエンディングノートや生前整理へ自然につながるのです。
Q&Aコーナー
Q1:思い出の品が捨てられません…
A:無理に捨てず、形を変えて残すのがおすすめです。写真に撮る、フォトブック化、作品を一部飾るなど。
Q2:どこまで業者に頼めばいいの?
A:量・体力・時間を基準に考え、大物や専門的処分は業者に依頼しましょう。必ず2〜3社に相見積もりを取ると安心です。(出典:国民生活センター(複数社から見積もりを))
Q3:家族と価値観が合わず、トラブルになりそうです…
A:ルールを決め、記録を残すと安心です。形見分けのルールを最初に決め、合意をメモや写真で残すのがコツです。
まとめと次の一歩
- 生前整理は「モノ・情報・心」の3分野から考えると進めやすい
- 判断の軸は「人・時間・物語」で迷いを減らす
- 写真やリスト化を使って「形を変えて残す」工夫を
- 完璧ではなく「少しずつ進める」のが大切
👉 今日できること:引き出し1段を10分で仕分けてみましょう。その一歩が、未来の安心と家族の笑顔につながります。
関連記事リスト
本記事は一般的情報の提供を目的とし、専門家の助言に代わるものではありません。個別の判断は専門家へご相談ください。