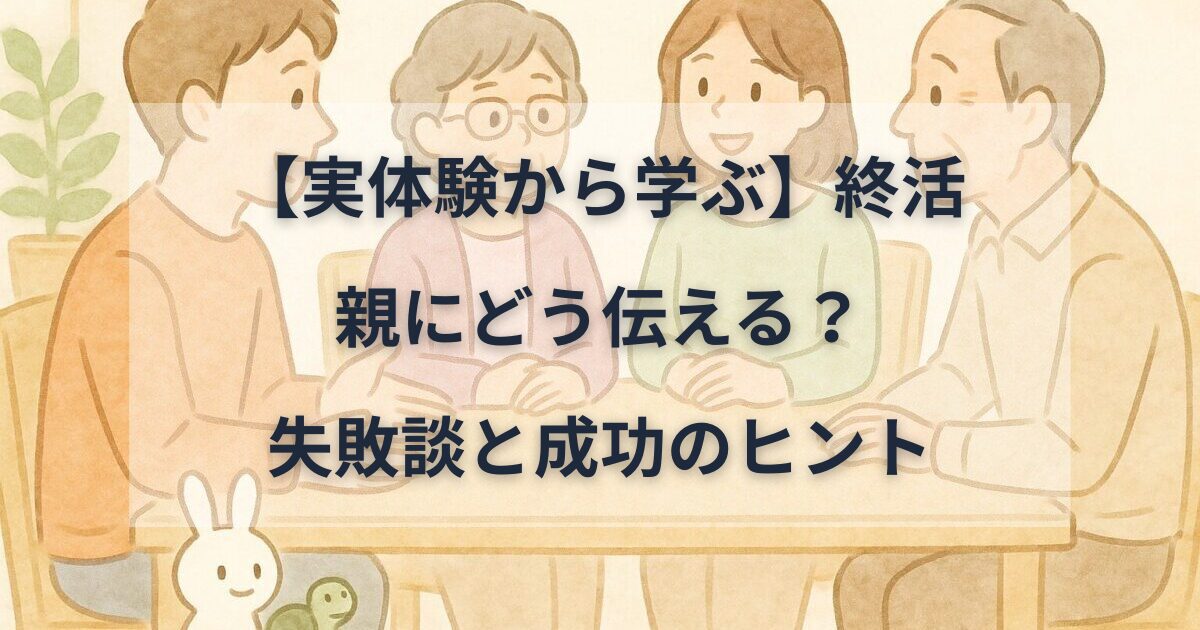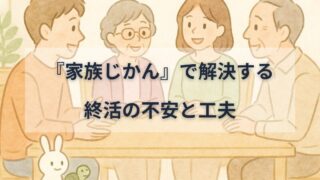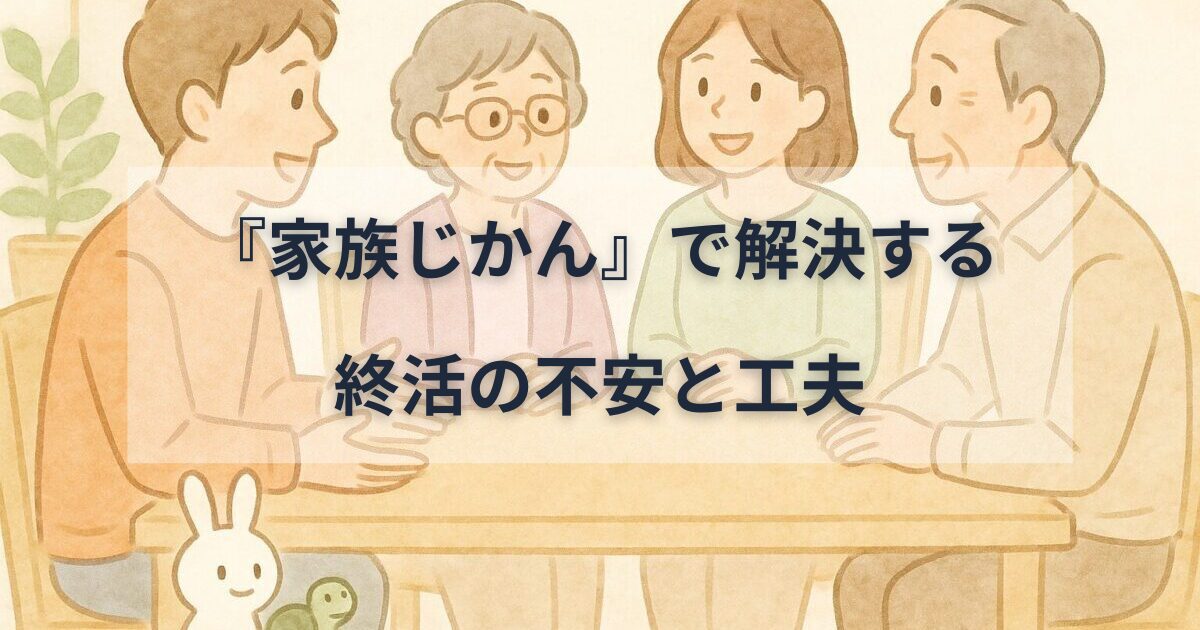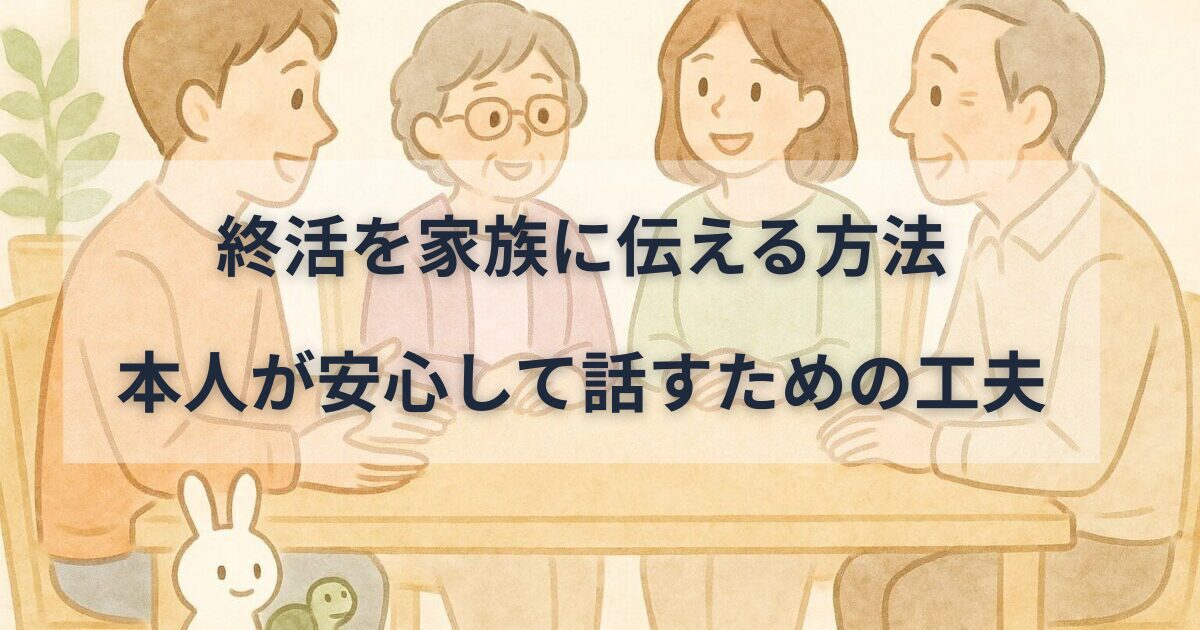親に「終活を考えてほしい」と切り出すと、多くの場合はこんな言葉が返ってきます。
- 「そんな話はまだ早い」
- 「縁起でもないことを言うな」
- 「心配しなくても大丈夫」
一見“拒絶”に聞こえるこれらの言葉。実はその裏には、死を意識したくない気持ちや、家族を心配させたくない思いやりが隠れています。
けれど、ここで話題を引っ込めてしまうと、いざというときに「何も聞いていなかった」「どうすればいいかわからない」と家族が混乱してしまうのです。
だから大切なのは、無理に迫るのではなく、受け入れてもらえる“伝え方”を工夫すること。
本記事では、断られた実体験とそこから生まれた成功例を紹介しながら、親が耳を傾けやすくなる声かけの方法を解説します。
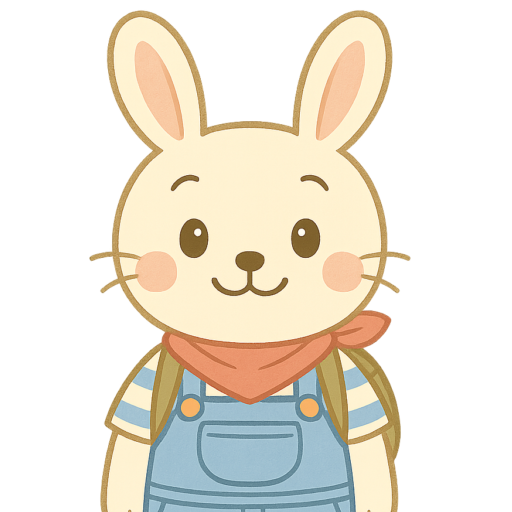
親に終活の話をすると、たいてい“まだ早い”って返されるんだよね…

その反応、珍しくないよ。でも理由を知れば、切り出し方も変わってくるんだ
親が終活を拒む理由と向き合う
「死を直視したくない」気持ち
食卓で、子どもが「もしものときのことを少し話しておこうよ」と切り出した瞬間。
箸を止めて「そんな縁起でもないこと言うな!」と声を荒げる親。空気が重くなり、話はそれ以上続かない――。こんな経験をした読者は多いはずです。
親世代にとって「終活」という言葉は、“寿命が目の前に迫っている”という宣告のように響きます。
だからこそ、無意識に耳をふさぎたくなるのです。
本当は心のどこかで準備の必要性を感じていても、「死」という現実を正面から受け止めるのは勇気が要るもの。
拒否の言葉は、恐れや不安を覆い隠すための防衛反応とも言えるでしょう。

たしかに…“まだ早い”って言葉の裏には、怖さや不安が隠れてるんだね。
「家族を心配させたくない」という優しさ
「私のことは心配しなくていい」「迷惑はかけないから」と返す親。
冷たく突き放すように聞こえるその言葉の裏には、実は深い思いやりが隠れています。
“弱った自分を見せたくない” “子どもには明るくいてほしい”――。
そんな親心が「まだ大丈夫」「そんな話は早い」という言葉に変わって表れるのです。
ある体験談では、父親に「葬儀やお墓の希望」を聞いたら「そんな話は縁起でもない」と手を振られたそうです。
数日後、父はふと「母さんのことはちゃんとやってやりたい」とつぶやきました。
その瞬間、拒否の言葉の裏に“守りたい気持ち”が隠れていたことに気づいたといいます。
表情や口調は反発に見えても、その根底には「家族を思う優しさ」があるのです。
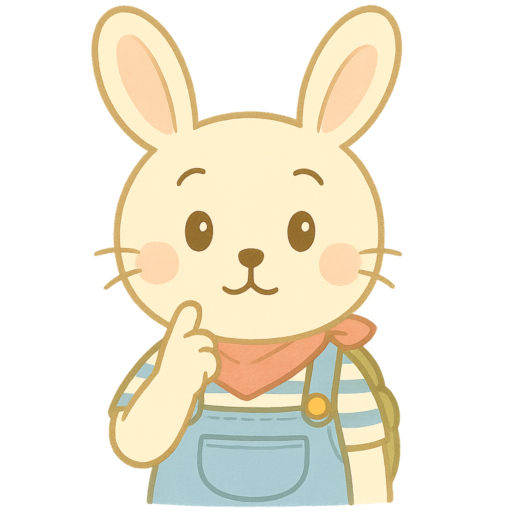
そっか…“迷惑かけたくない”って言葉は、優しさの裏返しなんだね。
「何から始めたらいいかわからない」という戸惑い
終活は、保険や財産、介護、葬儀、墓じまいなど、幅広いテーマが関わります。
「エンディングノートを書いて」と言われても、具体的にどこから始めればいいのか分からない人は多いでしょう。
親世代にとって、こうした情報は複雑で難解です。
子どもから突然「準備しておいて」と言われれば、かえって混乱し、面倒に感じてしまうのも無理はありません。
その結果、「まだ早い」と一歩引いてしまうのです。
ある母親は「私、何を残せばいいの?銀行口座のこと?それとも介護の希望?」と混乱して、
「ややこしいから考えたくない」と会話を打ち切ったそうです。
これは「考えたくない」という拒否ではなく、実際には「どこから始めればいいか分からない」というシグナル。
こうした戸惑いに寄り添い、「一緒に少しずつ整理していこう」と手を差し伸べることが大切です。
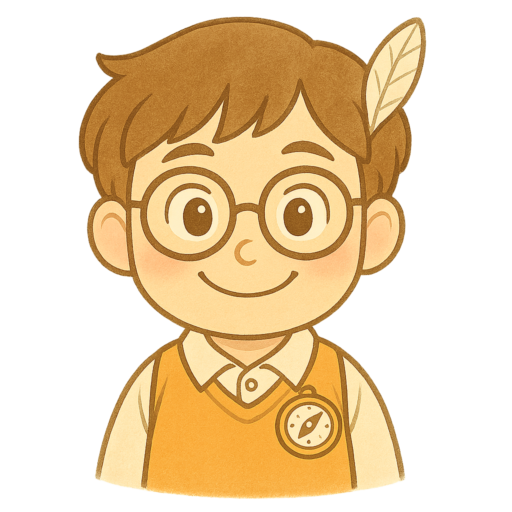
分からない”ってサインを見逃さないで。小さなところから一緒に手を動かすと、不安は和らいでいくよ。
こうすれば話せる!親が耳を傾けたきっかけ集
体調が落ち着いているときに「思い出整理」から始める
「母の体調が落ち着いている日に、昔のアルバムを一緒に眺めました。『この時の旅行、覚えてる?』と話すうちに、自然と“これから先にやりたいこと”という会話へとつながったんです。」
👨 終活ガイドのアドバイス
「“写真やアルバム”は、死を意識させずに未来の話へ自然に導ける効果的な入口です。
相談の現場でも『思い出を一緒に振り返ったら、気持ちが和らいで終活の話ができた』という声をよく聞きます。」
📊 豆知識
内閣府「令和6年版 高齢社会白書」によれば、終活に関連する準備をしている高齢者は全体の 60.0%。しかし実際にエンディングノートを作成している人は 8.3% にとどまっています。多くの人が「備えたい」と考えながらも、実際の行動に移せていないのが現実です。典:内閣府_高齢者白書)
第三者(親戚や友人)から自然に声をかけてもらう
「父に直接話したときは『まだ早い』と突っぱねられました。でも親戚のおじが『うちもそろそろ準備してるよ』と言った途端、父は『そうか…やっぱり考えた方がいいかな』と受け入れてくれたんです。」
👨 終活ガイドのアドバイス
「親世代は“子どもに心配をかけたくない”という気持ちが強いので、子どもの言葉は突っぱねやすいんです。でも、友人や親戚の声なら“同世代の意見”としてすんなり受け止められることが多いんですよ。」
「あなたのことをもっと知りたい」と昔話をきっかけにする
「“若いころの夢って何だったの?”と母に聞いたら、『本当はもっと旅行したかった』と笑って話してくれました。そこから『もし行けなくなったら、どうしたい?』という自然な会話に進めたんです。」
👨 終活ガイドのアドバイス
「親に『もっと知りたい』と伝えると、安心して話してくれるケースが多いです。
“死の準備”ではなく“あなたの歩んだ人生を知りたい”というスタンスで接すると、拒否の壁がやわらぎます。」
📊 豆知識
「同白書によると、終活準備の具体的内容では『財産・相続の整理』(41.2%)、『葬儀やお墓』(32.5%)、『介護の希望』(20.4%)が多く挙げられています。昔話をきっかけに“将来どうしたいか”を聞くことは、こうしたニーズに自然につながる入口になります。」(出典:内閣府_高齢者白書)
「もしもの話」を入口にする
「夕食時、近所の方が入院してペットの世話に困った話をしました。母は笑いながら『うちの犬はあんたにお願いね』と言ったのですが、その直後に真顔になって“ちゃんと書き残さないとね”とつぶやいたんです。笑いから真剣に変わる瞬間に、本音が見えました。」
👨 終活ガイドのアドバイス
「“もしも”の形で質問するだけで、重い話題がスッと入っていきます。
私の相談現場でも『もし手術になったらどうしたい?』という言葉がきっかけで、本人の希望を初めて聞けたというケースがありました。」
終活話でトラブルを起こさないコツ
せっかく話し合っても、「言ったつもり」「聞いたつもり」で終わってしまうことがあります。
家族との終活は“共有”が大事。次の3つを意識すると安心につながります。
- 話した内容を必ず誰かがメモする
- 次の話し合いではそのメモを使う。
- 兄弟姉妹など複数の家族に伝えておく(終活本人の許可をもらう事)
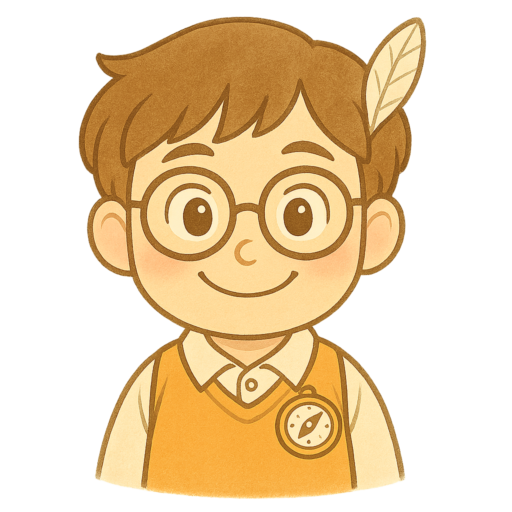
“隠す”じゃなくて“共有する”。それが家族への思いやりなんだ
Q&Aコーナー
Q1. 親が強く拒否する場合、どうすれば?
無理に迫らず、まずは“自分からやってみたよ”と見せるのが一番。話すきっかけは、時間がたってから自然に訪れることもあるんだ。
Q2. エンディングノートは必須?
必ずしもノートじゃなくてもいいんだよね。メモや口頭でも大事なのは“共有”。ただ形に残しておくと安心感はぐっと増すよ。
まとめと次の行動

終活の話は、押しつけじゃなく“家族で安心をつくるコミュニケーション”なんだ。
今日お伝えしたポイントを、ぜひ思い出してみてね。
- 話したことは「共有」してこそ意味を持つ
- 親が拒むのは「死への恐れ」「家族への優しさ」「戸惑い」が理由
- 写真整理や昔話、第三者の力、“もしもの話”などでやわらかく切り出せる
関連記事リスト
免責
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、医療・法律等の専門家による助言に代わるものではありません。